大阪大学が“顔パス”入館を実現 附属図書館で顔認証ゲートを導入、国立大で初の試み
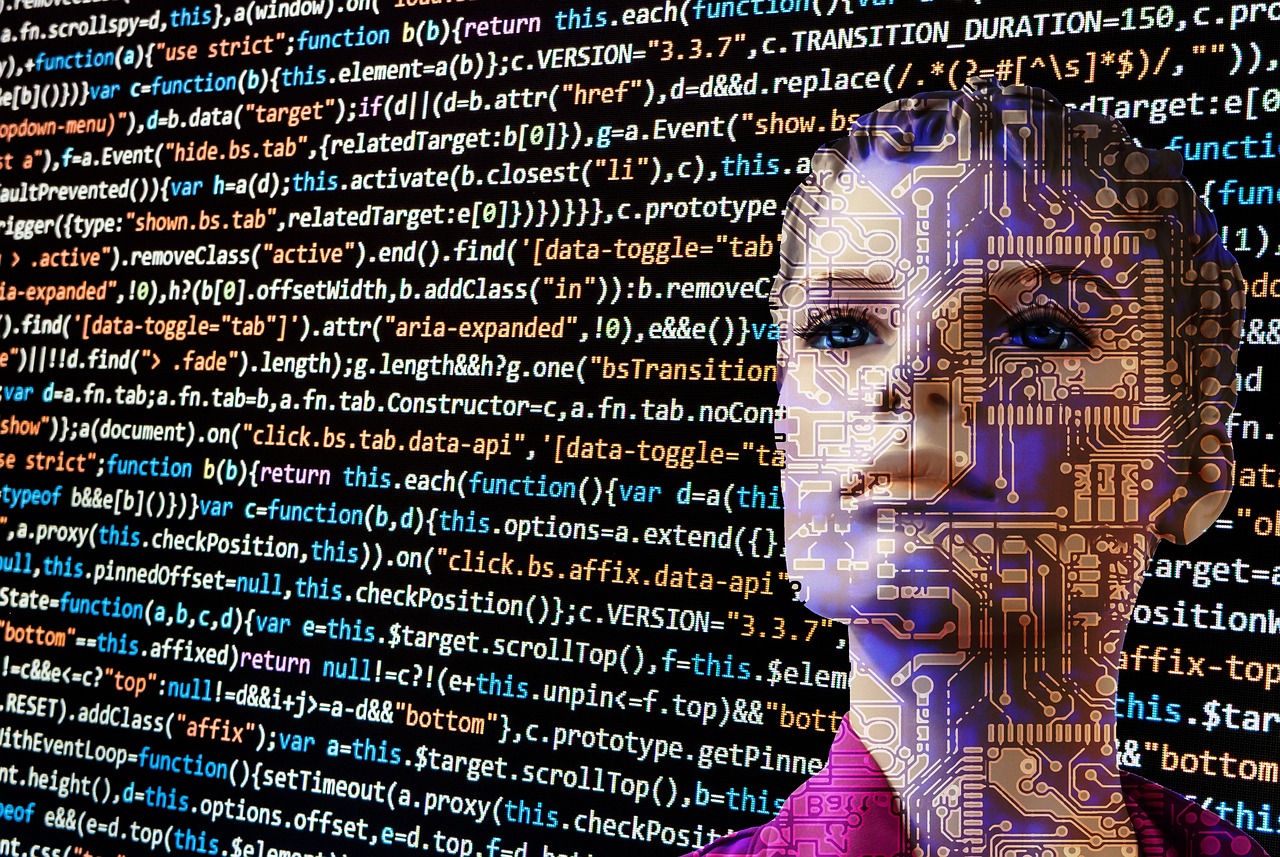
大阪大学は2025年4月21日、附属図書館4館に顔認証技術を導入すると発表した。国立大学として初の試みであり、5月から運用を開始する。利便性向上と業務効率化を目的とした本施策は、今後の教育機関における認証技術導入の先例となりそうだ。
国立大学で初の顔認証システム導入、その背景と技術的枠組み
大阪大学が運用を開始する顔認証入館システムは、同大学の豊中キャンパスの総合図書館、吹田キャンパスの生命科学図書館と理工学図書館、箕面キャンパスの外国学図書館、以上の4館の入館ゲートに導入される。今秋には自動貸出返却装置でも顔認証が可能となる見込みである。
このシステムは、同大学が構築した統合ID基盤「OUID」(※)と連携しており、学生や教職員が事前に顔写真を登録することで、学生証の提示なく本人確認が行えるよう設計されている。加えて、デジタル学生証や教職員証に付帯するQRコードにも対応しており、柔軟な認証手段を提供する。
技術開発にはパナソニック コネクトと紀伊國屋書店が携わり、高精度な認証精度とセキュリティ性を両立させた。大阪大学では2024年から顔認証による入場管理の実証を重ねており、今回の図書館導入はその成果の一環といえる。
背景には、利用者の利便性向上と業務効率化の双方を図る狙いがある。非接触かつ即時性のある顔認証技術を採用することで、混雑緩和やカード紛失といった従来の課題解消が期待される。
※ OUID(Osaka University ID):大阪大学が独自に構築した統合ID管理システムであり、大学内の各種サービスと連携して本人認証を行う基盤技術である。
図書館から広がる認証技術の活用と、利便性の裏に潜むプライバシー課題
顔認証ゲートの導入は、図書館の出入りをスムーズにするだけでなく、大学運営にも新たな効率化をもたらす可能性を持つ。利用者にとっては、学生証を取り出す手間が省けるため、ストレスフリーな入館体験が得られる。また、貸し出しや返却の処理もスピーディーに完結し、利便性は飛躍的に向上する見通しだ。
一方、こうした技術導入には慎重な運用が求められる。
顔認証は個人情報の中でも極めてセンシティブな生体情報を扱うため、誤認識や不正利用、さらにはデータ漏洩といったリスクに対する対策が不可欠である。大阪大学はセキュリティ強化とプライバシー保護の両立を掲げているが、今後の運用過程で利用者との信頼関係構築が鍵を握るだろう。
大学側は、今後この技術を会議室や授業・試験の出欠確認にも展開する構えであり、教育現場におけるデジタル化の一環として広がりを見せると考えられる。約3万人の学生・教職員が対象となるため、システムの規模と精度が問われる局面に差し掛かっている。
この動きは、他の大学や教育機関、さらには企業の勤怠管理などにも波及する可能性を含んでおり、顔認証技術の社会実装が現実味を帯びてきたといえる。利便性とセキュリティのバランス、そして透明性ある運用が、今後の展開の鍵を握るだろう。









