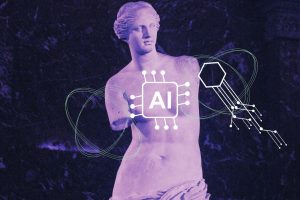兵庫県相生市、生成AIで作成したモデルが登場する観光PR動画を公開
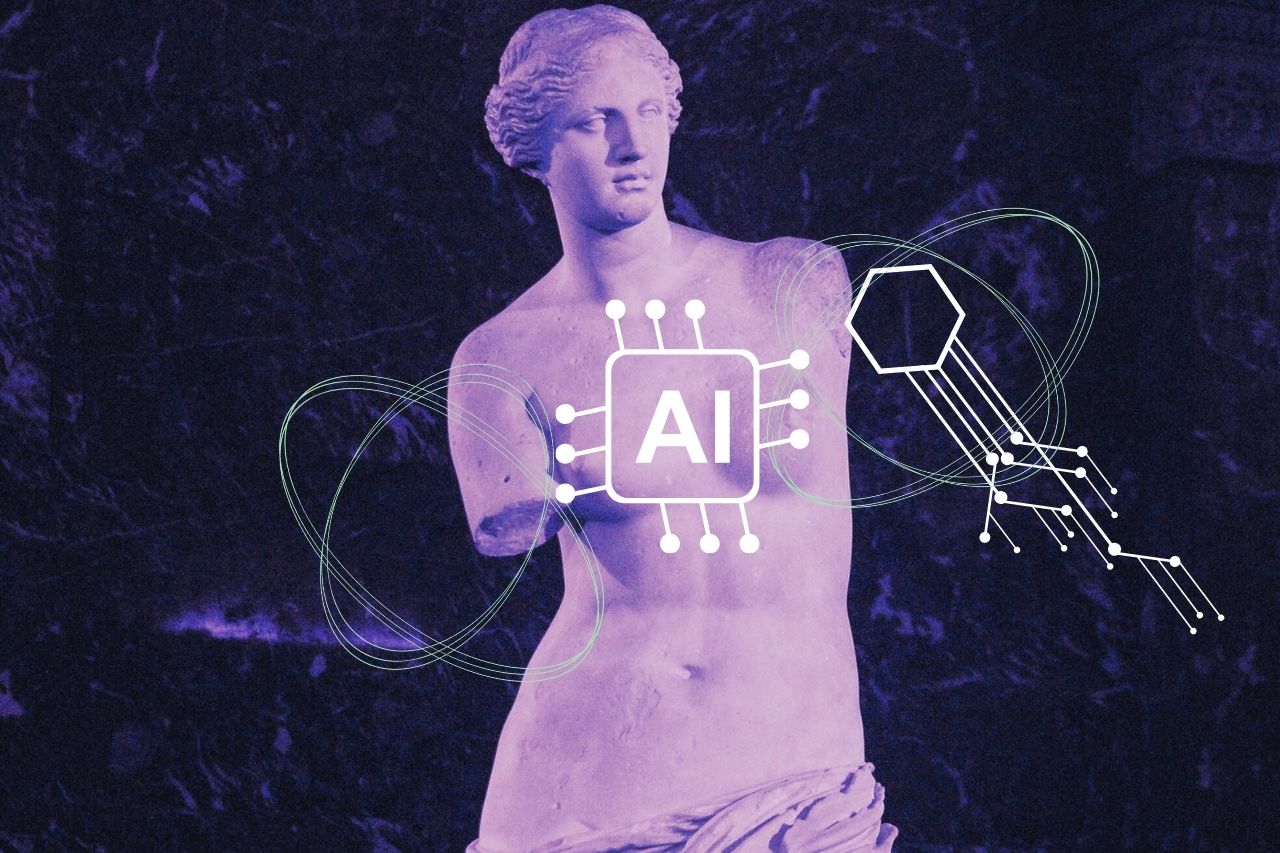
2025年4月3日、兵庫県相生市が生成AIを活用した観光PR動画「#相生ランウェイ」をYouTube上で公開した。同月8日にはInstagramでも公開されている。
生成AIが創り出したモデルが市内の観光地を颯爽と歩くこの映像となっており、リアルで洗練されたビジュアルと動きによって視聴者に強い印象を与える構成だ。
生成AIで描く“理想の観光モデル”、地方PRの表現力が一新される
今回公開された動画では、30歳代の市職員の男女2人をベースにしたAIモデルが市内の観光名所を巡る様子が描かれている。
相生市は、定住人口の増加を目指し、市の知名度を高めるためにこのPR動画を制作したという。
背景には、近年飛躍的に進化している生成AIの技術がある。特に動画生成においては、画像認識と動作シミュレーションを組み合わせることで、より自然な人物の挙動が可能になってきている。
今回の動画も、相生市の観光名所「万葉の岬」「羅漢の里」「道の駅・あいおい 白龍ぺーロン 城」の風景と合成されたバーチャルモデルが違和感なく融合しており、プロモーションとしての完成度は高い。
動画は3分弱という短さながら、テンポの良い構成と音楽により視聴者の離脱を防ぎつつ、都市部在住の若年層にもリーチする設計となっている。
生成AIの応用としては、既に広告やファッション業界で活用例が増えているが、自治体による本格導入は珍しい。
市企画広報課は「モデルのように相生をランウェーにしSNSで発信してほしい」と拡散を促している。
今後の展望
今回の相生市の事例は、生成AIの地域PR分野への応用がいよいよ本格化し始めたことを示すものであり、他自治体にも波及する可能性は高いと考えられる。
今後、観光振興や定住促進を目的としたプロモーションにおいて、仮想モデルを活用した動画やビジュアルコンテンツが増加するだろう。
特に、生成AIによるモデル制作は、自治体ごとに「理想の地域イメージ」を構築するツールとしての価値を持つ。リアルな人物に依存しないぶん、モデルの個性や世界観を自由にデザインできるため、地域ごとの差別化を図りやすくなる。
一方で、生成AIが制作した映像が一般に流通する機会が増えれば、視聴者の側でも「これは本物か?」という問いを持ちやすくなる。
その結果、動画コンテンツの“信頼性”や“真実味”がますます重視されるようになり、映像の制作側にも「説明責任」や「出典明示」の文化が求められていくことになるだろう。
さらに、AI生成物の透明性と倫理的配慮が社会的議論の対象となる中で、今後は自治体や行政機関も、単なる技術導入にとどまらず、「AIとの付き合い方」そのものが問われる時代に突入していくことになるとみられる。
生成AIは地方創生の“新たな武器”となる可能性を秘めているが、それをどう使いこなすかは、自治体ごとのセンスと運用ルールにかかっている。