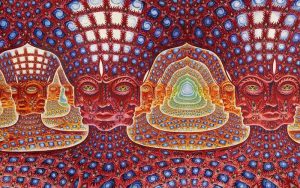プログラミング教育事業者が 「AI Coding」商標出願 コミュニティの批判を受け取り下げ
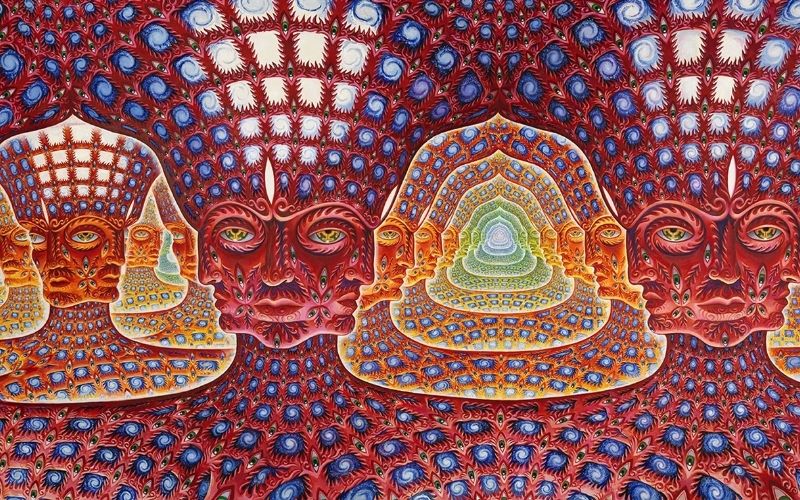
2025年4月16日、日本国内で広く使われる技術用語「AI Coding」の商標出願が、SNS上の批判を受けて取り下げられた。
申請を行ったプログラミング教育事業・アパレルブランド事業を展開するミチガエル社の代表は意図を説明し謝罪。
技術用語の独占と知的財産のあり方が問われる事例となっている。
「一般化した用語」を私企業が商標化
今回の騒動は、2025年4月10日頃、X(旧Twitter)上の「商標速報bot 8号」アカウントが「AI Coding(※)」の商標出願を紹介したことに始まる。
この投稿に対し、エンジニアやクリエイターから「一般的な言葉を商標化するのか」「技術共有を妨げる」といった批判が広がった。
4月15日には、メルカリの生成AI推進担当であるハヤカワ五味氏がnoteで懸念を表明し、「AI Coding」が特許庁によって登録されれば、教育や創作活動の自由が阻害されかねないと警鐘を鳴らした。
特許庁の情報提供制度を活用し、異議申し立てを行う意向も示していた。
こうした批判を受けて、出願者であるミチガエル社の今西航平代表は4月16日、自身のXアカウント上で商標出願を取り下げたと発表。
「サービスに関連するリスク回避を意図していた。社会的な影響への配慮が不足していた点を深く反省している」として謝罪し、言葉の公的性を尊重する姿勢を明らかにした。
「AI Coding」は、AI技術を活用してコードを書く行為を指す用語として、ZennやQiitaなどのエンジニア向けメディアでも長年にわたり使用されてきた。
特定企業による独占的な商標化は、オープンな知識共有を重視するエンジニア文化と真っ向から衝突する事態となった。
※AI Coding:
人工知能(AI)の補助を受けながらソースコードを記述する手法や行為を指す言葉で、近年の生成AIの普及に伴い、ソフトウェア開発分野で急速に広がっている用語。
技術用語の商標化の問題点
「AI Coding」騒動が広がった背景には、一般化した言葉を私的に商標登録しようとした事への警戒感があった。
今回のケースにおいても、単なる法的手続きを超えて、「誰もが使えるべき言葉を囲い込むのか?」という倫理的・文化的な観点が強く問われた。
技術の進化とともに言葉もまた共有資産となりつつあるなかで、知的財産制度とオープンなコミュニティ文化のバランスが課題として浮かび上がっている。
今西氏が出願を取り下げたことで、ハヤカワ五味氏も異議申し立ての活動を中止した。
今回のケースでは、今西氏が批判を受けて柔軟な対応をしたことで、一般に広まった用語が囲い込みされるケースは回避できた。
それでも、騒動になっていなかった場合は、「AI Coding」が商標登録されてしまうことを考えると、楽観視はできない。
ハヤカワ氏は集まった支援金約10万5200円を、今後も「誰もが使えるべき表現の囲い込みを防ぐ活動」に使うと表明しており、問題提起は続いている。
この一件は、今後も発展し続けるAI技術や開発文化において、言葉や概念の所有権が誰に属するべきかという問題を象徴的に浮き彫りにした。
技術と言葉が密接に結びつく現代において、透明性と共有の精神が一層求められていると言えるだろう。