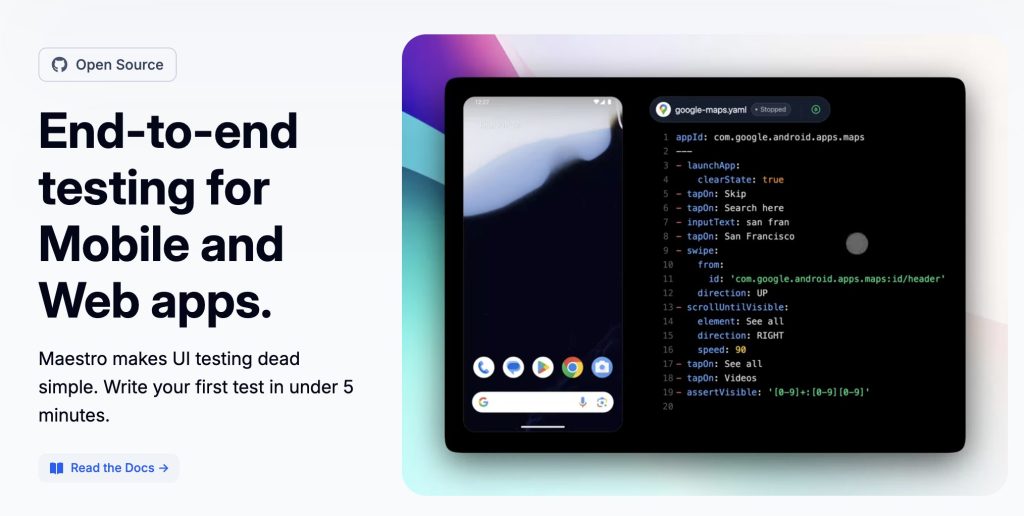生成AIで教育はどう変わるのか 東大・坂村健名誉教授が語る「教育改革国民運動」の現実味

2025年5月12日、東京で開催された「教育改革国民運動」シンポジウムにて、東京大学の坂村健名誉教授が生成AIによる教育変革の必要性を強調した。
生成AI時代に教育の常識は通用しない 坂村健氏が指摘する制度疲労と再設計の必然
5月12日、東京で行われた「教育改革国民運動」シンポジウムでは、生成AIの進化に伴い、教育制度の根幹を見直すべきだとの議論が展開された。
同運動は、昨年秋に経済界の有志により発足したもので、日本の教育が現代社会に対応しきれていないという危機感を背景としている。
東京大学名誉教授である坂村健氏は、講演の中で大学教育における「教育設計の再構築」が不可欠であると述べた。生成AIが学生の知的活動の一部を代替できる時代において、従来型の知識詰め込み型カリキュラムはすでに限界に達しているという認識である。
また、点数による数値評価から脱却し、面接やディスカッションなどを通じた「人物評価」へと移行する必要性を指摘した。これは、生成AIによって答案の作成さえも自動化できる現状を踏まえると、不可避な変化とも言える。
こうした教育の再定義は、一部の理想論ではなく、経済界からの強い要請でもある。シンポジウムで紹介された全国1123社の中小企業アンケートでは、4社のうち3社(73%)が現在の教育制度は実社会で役に立っていない」と回答した。
企業が求めるのは、知識だけでなく、応用力やコミュニケーション能力を備えた人材である。
教育の役割が単なる学力の育成から、社会に通用する人間力の涵養へと変わりつつある現実が浮き彫りになった。
点数主義から人物評価へ 評価制度改革が導く教育の未来像
今回のシンポジウムで示された方向性は、単なる提言にとどまらない。「教育改革国民運動」は今後、大学入試制度をはじめとした具体的な制度改革の提案を続けていくと表明している。特に、評価基準を点数から人物評価にシフトする方針は、入試制度や授業設計を根本から変えるインパクトを持つ。
この改革の先には、学生がAI時代に対応可能なスキルを身につけることが求められている。AIと共存しながら思考する力、自ら課題を設定し解決する力、他者と協働する力など、従来の「正解を出す力」とは異なる資質が重要視されるようになるだろう。
すでに海外では、ポートフォリオ評価やプロジェクトベースの学習(PBL)など、学びのプロセスそのものを重視する教育への転換が進んでいる。
一方で、こうした制度改革には時間とコストがかかる上、評価の公平性や標準化といった新たな課題も生まれることは否定できない。
しかし、教育を未来の社会づくりの根幹と捉えるならば、既存制度に安住する余裕はない。
生成AIの登場は、教育現場に突きつけられた変化の必然を明らかにしたにすぎない。