文科省が検定結果を公表 高校教科書に「生成AIのリスク」続々
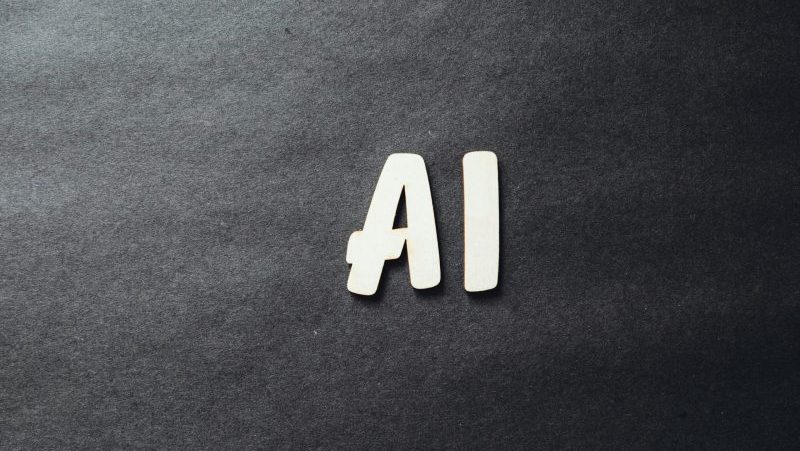
2025年3月25日、文部科学省は2026年度から主に高校1年生が使用する教科書の検定結果を公表した。
生成AI(人工知能)のリスクに関する内容が広く取り上げられ、情報・英語・家庭など多岐にわたる教科で48点の教科書が合格したことが明らかになった。
生成AIのリスクが高校教育に本格導入 多教科で取り上げられる背景とは
情報漏洩や著作権侵害といったリスクが現実の問題として浮上している中、高校教育においてもデジタルリテラシーの強化が急務とされている。その結果、今回の教科書検定では、生成AIに関連する記述が急増した。
文部科学省が公表した検定結果によれば、情報、英語、家庭など8教科にわたる計48点の教科書が合格した。
とりわけ情報の教科書では、AIが作成したコンテンツが他者の著作物に酷似することで著作権問題が生じるケースや、入力した個人情報が無断で使用される可能性について具体例を交えて詳しく解説しているようだ。
教科書のAI情報は学生にとって影響力が高い
高校教科書に生成AIのリスクが盛り込まれたことには、いくつかのメリットがある。
まず、若年層の段階からAIリテラシーを育てることで、技術に対する理解と正しい活用法が身につくだろう。
情報、英語、家庭といった複数の教科で取り上げられたことで、AIの影響が多面的であることが自然に伝わる構成となっているため、単に技術の利便性だけでなく、著作権やプライバシーといった社会的な問題と結びつけて考える機会が生まれるだろう。
一方で、課題もある。
リスクに焦点を当てすぎると、生成AIそのものに対して過剰な警戒心を持たせかねない。
技術に対する偏った印象が形成されれば、今後の活用に消極的になる可能性もある。
また、教員側の理解や指導力にも差があると予想され、教科書に記載されている内容が生徒に正確に伝わるとは限らない。
教科書に内容を盛り込むだけでは十分とは言えないだろう。
今後、生成AIは日常生活から産業界まで、より広範に浸透していくと考えられる。
教育現場も例外ではなく、単なるリスク教育にとどまらず、AIを「どのように活かすか」という視点が求められることになるだろう。
今回の教科書改訂はその第一歩と位置づけられるが、今後はより実践的なカリキュラムや探究学習への応用も進んでいく可能性がある。












