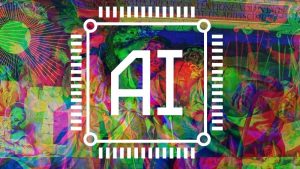Algomaticが「にじボイス」終了決定 AI音声と権利保護の葛藤が浮き彫りに
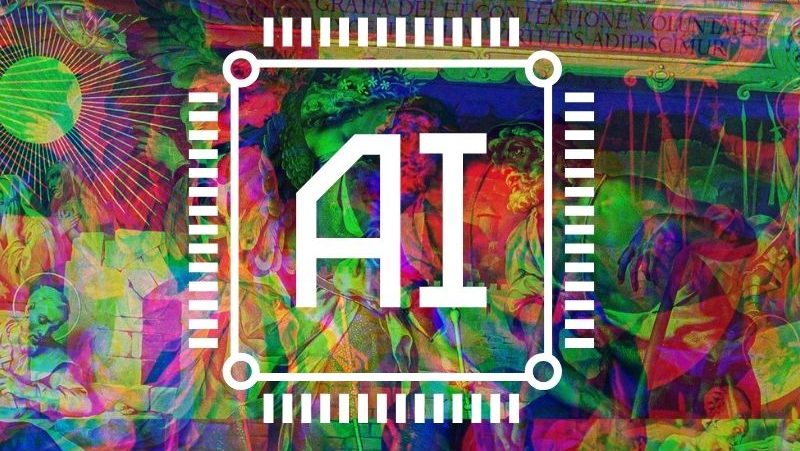
2025年11月21日、国内AI企業Algomaticは音声生成サービス「にじボイス」を2026年2月4日に終了すると発表した。俳優団体からの複数の指摘に対し法的問題は確認されなかったが、同社は理念との整合性から事業終了を選択した。
俳優団体の指摘を受けAlgomaticが「にじボイス」全体の終了を発表
Algomaticは、AI音声生成プラットフォーム「にじボイス」を来年2月4日で完全終了すると明らかにした。
同社は9月、日本俳優連合から33体のキャラクターボイスが「実演家の声に似ている」との指摘を受けたが、社内調査の結果、権利侵害は確認されなかった。
それでも、利用者や実演家に心配や懸念を与えることは本意ではないと判断し、当該ボイスの提供を停止した。
しかし、11月17日に追加で20体の削除要請が届いたことで状況は一変した。
こちらも法的問題は認められなかったものの、同社は声の権利を守るプラットフォームとして、「『声が似ている』とご本人等が不安に思っていらっしゃるのに、それは、主観であるという主張をすることが、生身の人間に対してどう感じられるのか、と言う問いを何度も考え続けました」と説明。
「AIと人とがぶつかりあうのではなく、より良い世界をつくる」という信念を考えあわせた時に、サービス全体の終了を決断したという。
さらに、日本俳優連合への誹謗中傷を控えるよう強調し、ユーザーへの影響や詳細スケジュールは後日案内するとしている。
今回の判断は、事業継続よりもその理念を優先した格好であり、企業としての価値観を示す象徴的な判断と言える。
AI音声の基準作りが加速へ 権利保護と革新の両立が問われる局面に
今回の終了判断は、AI音声ビジネスにおける「声の類似性」をどう扱うべきかという根本的な課題を浮き彫りにした。法的に問題がないケースでも、実演家側が不安を抱けば企業は対応を迫られる可能性が高まっており、業界のリスク管理水準は一段と厳しくなるとみられる。これはAI企業にとってデメリットだが、クリエイター保護の観点では重要な前進でもある。
今回の判断は業界基準制定の呼び水となるだろう。声の特徴量の扱い、学習データの透明性、生成モデルの説明責任といった論点が顕在化し、適切なルール形成が進む契機になりうる。特に音声権の解釈が曖昧な現状では、事業者・実演家・ユーザーの三者が納得する枠組みが不可欠になっていくだろう。
一方、AI音声市場は拡大基調にあり、サービス終了による空白を埋める形で新規プレイヤーが参入する可能性もある。新規参入者の理念によっては、同様の問題が再発するリスクも拭えない。
今後は、企業が生成AIの社会的受容性をどこまで重視するかが成長の鍵を握るとみられる。AIと人間が対立せずに共創するための指針作りは避けて通れず、今回の決断はその議論を加速させる契機になるだろう。
関連記事:
声の保護と多言語化に取り組む新団体が発足 生成AI時代の声優の権利保護と海外展開を視野に