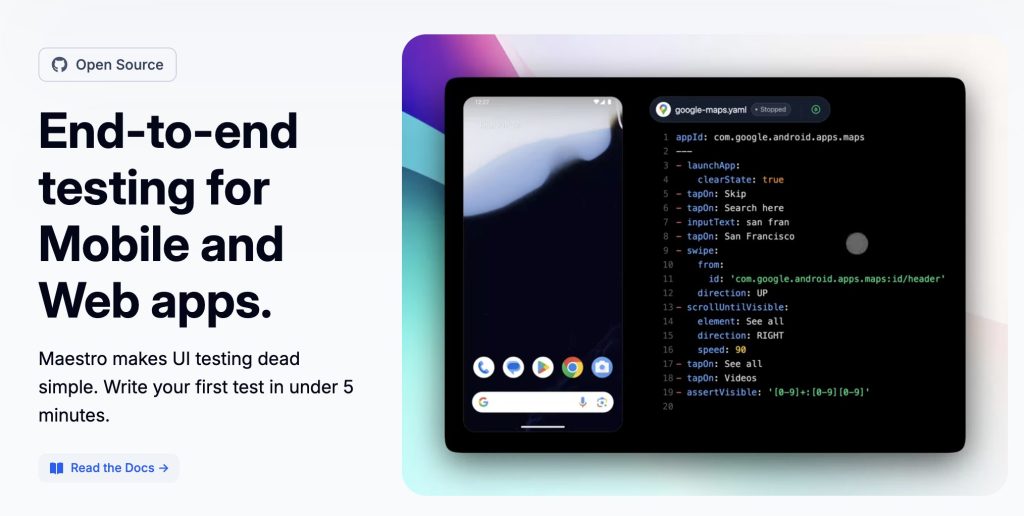共同通信、AI加工写真を撤回 報道の信頼性と編集体制に改めて焦点
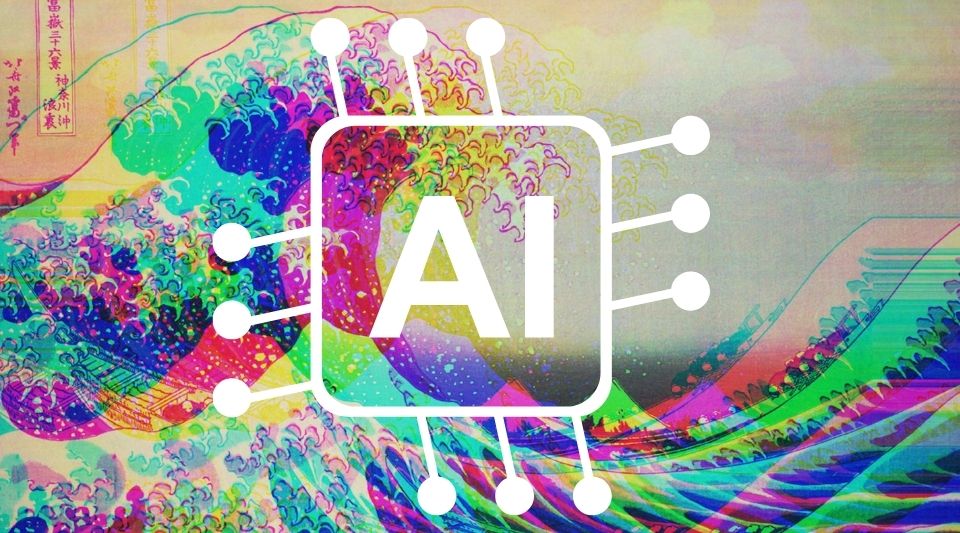
2025年11月2日、共同通信社は、屋久島で撮影されたとして配信した「ウミガメの子ガメをくわえているタヌキ」の写真を取り消した。提供元が画像の鮮明化に生成AIを用いていたことが確認されたためで、報道写真の真正性が改めて問われている。
生成AI加工が判明し、共同通信が写真を取り消し
共同通信は2025年10月20日に配信した一枚の写真を撤回した。
写真は鹿児島・屋久島でタヌキがウミガメの子ガメをくわえる様子を捉えたとして、ウミガメの生態系被害を報じる記事に添えられていた。
しかし配信後、「生成AIの画像ではないか」という指摘が寄せられ、社内で精査が行われた。
調査の結果、写真はウミガメ保護団体の協力者が監視カメラ映像をもとに生成AIツールを使用して画質を向上させていたことが判明した。もとの画像に比べ、タヌキの毛並みが不自然なほど鮮明になり、子ガメの向きも変化していた。
記事の内容そのもの、つまりタヌキがウミガメの卵や子ガメを捕食する事例が屋久島で発生しているという点には誤りはない。
共同通信は「報道用途の写真・動画に生成AIを原則使用しない」と社内指針で定めており、今回の加工はその方針に反すると判断した。
同社は今後、提供写真に対する加工有無の確認を徹底し、再発防止策を講じるとしている。
報道の「透明性」と技術活用の両立は可能か
今回の事例は、報道機関が生成AI技術とどう向き合うべきかという構造的課題を示している。画像の補正や鮮明化は、取材現場で避けられない技術的要請に応える手段となりうる一方で、過度な加工は「何が現実だったか」を曖昧にし、誤った印象を強化してしまう危険がある。
メリットとして、生成AIは低画質素材の補完や速報性の向上に寄与する点が挙げられる。
しかし、加工と改変の境界は曖昧であり、編集部や提供元が意図しないまま「事実の形状」が変化するリスクを無視することはできない。特にSNS時代では、画像一枚がニュース本文以上の影響力を持つことさえある。
今後は、報道現場におけるAI活用の基準づくり、加工履歴の明示、検証プロセスの標準化といった透明性強化が求められるだろう。
技術を排除するのではなく「どの範囲で使うか」を社会的に共有することが信頼回復の鍵になると言える。