インド政府、AI生成物への識別ラベル義務化へ ディープフェイク拡散防止で規制強化案を公表
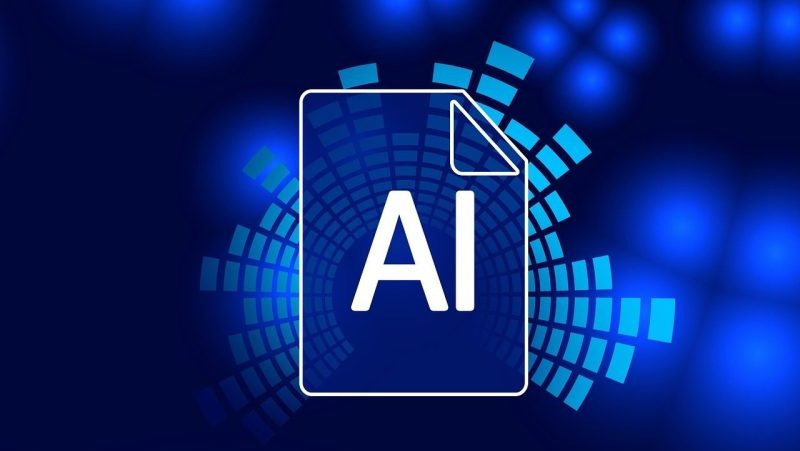
2025年10月22日、インド電子・情報技術省はAI(人工知能)およびソーシャルメディア企業に対し、生成コンテンツへの識別ラベル付与を義務付ける規制強化案を公表した。ディープフェイクや偽情報拡散の抑止を目的とし、11月6日まで意見公募を実施する。
AI生成コンテンツに「識別義務」導入へ 透明性確保を法制化
インド政府が公表した新たな規制案では、すべての一般向けAI生成コンテンツに対し、明確に識別可能なラベルを表示することを義務付ける。画像や動画の場合は画面の少なくとも10%、音声クリップでは再生時間の冒頭10%にマーカーを表示するよう求める内容だ。
これにより、視聴者がAI生成物を容易に見分けられる仕組みを整える狙いがある。
また、ソーシャルメディア企業には、ユーザーが投稿時にAIによって生成されたかどうかを申告する仕組みを導入し、「抑制と均衡(チェック・アンド・バランス)」を確保するための適切な措置を講じることが求められる。
電子・情報技術省は「全ての一般向けAI生成メディアに対して、視覚的なラベル付け、メタデータの追跡性、および透明性を確保する」と説明している。
10億人を超えるインターネット利用者を抱える同国では、フェイクニュースが宗教的・社会的対立を引き起こす事例が懸念され、特に選挙期間中のディープフェイク(※)動画流通を重大なリスクと見ている。
こうした背景から、今回の規制案は国家安全保障および公共秩序の観点からも重要な措置とされる。
同様の法整備は欧州連合(EU)や中国など主要国がすでに進めており、インドも国際的なルール形成の潮流に加わる格好だ。
※ディープフェイク:AI技術で実在人物の顔や声を合成し、本人が発言・行動しているように見せかける偽造コンテンツ。政治利用や詐欺などへの悪用が国際的な問題となっている。
透明性と表現の自由の両立が課題 AI時代の情報倫理を問う
識別ラベル義務化は、生成AIの透明性と社会的信頼を高めるうえで大きな意義を持つと言える。今回の検討事例のようにラベル表示によって誤情報拡散を抑えられれば、政治的対立や民族間の衝突を防ぐ効果が期待できる。
また、広告・教育・行政といった分野でのAI活用がより健全に進む可能性もあるだろう。
一方で、創作や表現の自由への影響も無視できない。AIを用いたアートや風刺など、意図的に曖昧さを残す表現が制限される懸念があるほか、過剰なラベル表示がユーザー体験を損なう恐れもある。
さらに、技術的な追跡や監視の強化がプライバシー侵害につながるという懸念も残る。
透明性と自由のバランスをどう取るかが次の焦点になると考えられる。
また、インドはAIスタートアップの急成長国でもあり、過度な規制が技術革新の足かせになる可能性もある。
政府は今後、業界や市民社会との対話を通じ、AI生成物の信頼性確保と創造的自由の共存を探ることが求められるだろう。












