「AI対AI」の時代に備えを 平デジタル相が退任会見でリスク管理の重要性を訴え
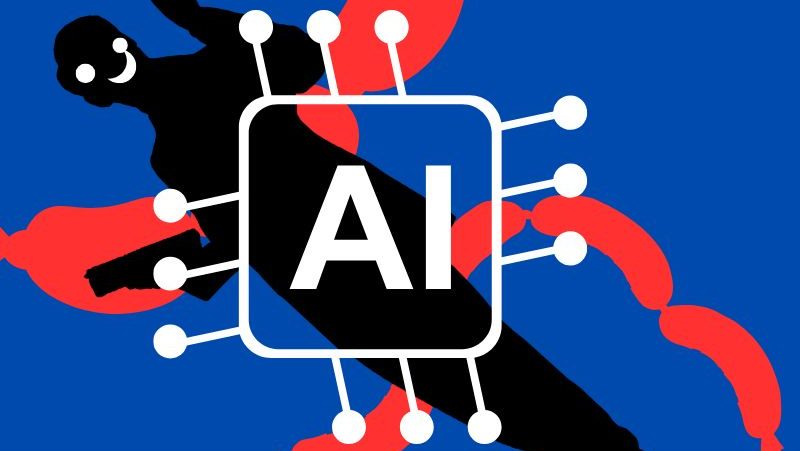
2025年10月21日、平将明デジタル相が退任記者会見を開き、AI(人工知能)の急速な進化によって生じるサイバーリスクへの警戒を呼びかけた。「オフェンスとディフェンスは最終的にAI対AIになる」と述べ、国と行政が専門人材や知見を共有できる環境整備の必要性を強調した。
AI進化がもたらす新たな脅威 平デジタル相が官民連携の強化を訴え
平将明デジタル相は21日、デジタル庁で行った退任会見で、AI技術の高度化に伴うサイバー攻撃リスクの深刻化を警告した。同氏は「サイバー攻撃のオフェンス(攻撃)とディフェンス(防御)は最終的にAI対AIになる」と述べ、従来型のセキュリティ対策では限界があるとの見方を示した。
2024年10月に第4代デジタル相として就任した平氏は、在任中に生成AIを行政に活用する「ガバメントAI」構想を推進。デジタル庁では職員が共通で利用できる生成AI環境「源内(げんない)」を内製開発し、業務効率化や政策立案支援を進めてきた。
こうしたAI実装の基盤整備が進む一方で、平氏は「イマジネーションが働かないと(AIの進化に伴うリスクに)対応しきれない」とも強調した。
政府は2025年5月に「能動的サイバー防御(※)」関連法を成立させた。
平氏はこれらの枠組みを評価しつつ、「同盟国、同志国とウィン・ウィンの関係が築ける可能性が出てきた」と述べ、国際協力の深化を訴えた。
※能動的サイバー防御:国家がサイバー攻撃を受ける前に、脅威の兆候を検知・無力化する防御手法。従来の受動的対策に比べ、先制的な対応を重視する。
AI行政の進化とリスク管理 透明性・倫理の確立が焦点に
平氏の退任後、デジタル庁が直面する課題は、AI活用とリスク管理のバランスであると言える。
AIによる自動分析や意思決定支援は行政の効率を飛躍的に高める一方で、誤作動や情報漏えい、アルゴリズムの偏りといったリスクを伴う。
AIの活用範囲が広がるほど、透明性と説明責任が問われることになるだろう。
行政分野では生成AIが文書作成や住民対応を担う場面が増えつつあるが、データの扱い方や判断基準を明確にしなければ、市民の信頼を損なう可能性がある。今後は、AIの利便性を社会全体で享受しながらも、情報の取り扱いをめぐる倫理基準の整備が急務となるだろう。
一方で、平氏が構想した「ガバメントAI」は、行政業務の生産性を高める突破口になりうる。内製開発により、国内の技術力を育成しつつ安全性を確保する点は大いに評価できると言えるだろう。
デジタル庁には今後、AIのリスクを最小化しつつ社会実装を加速させる「知的防御力」の確立が求められるとみられる。












