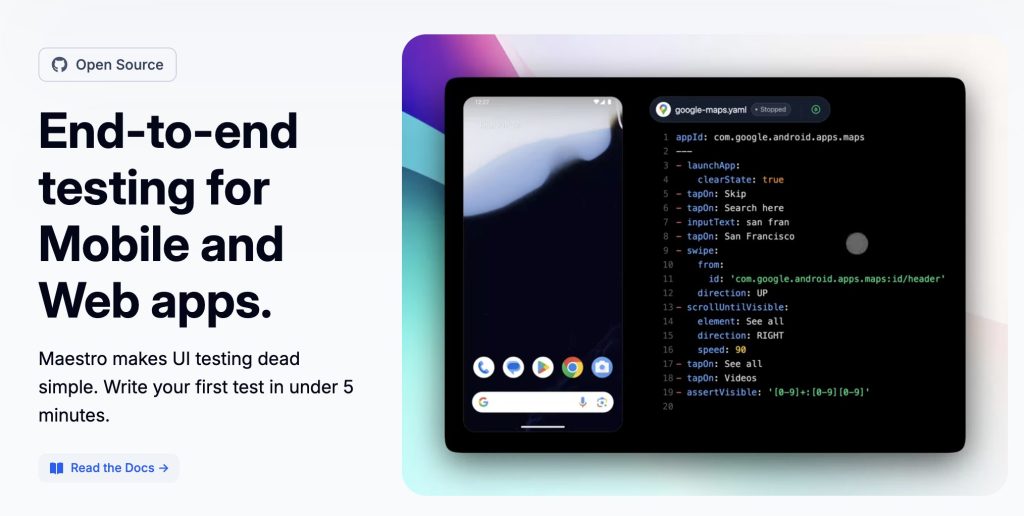PFN・さくらインターネット・NICT、国産生成AI大規模言語モデルを共同開発へ

2025年9月18日、Preferred Networks、さくらインターネット、情報通信研究機構(NICT)は、国産生成AIのエコシステム構築に向けて基本合意を結んだ。日本語に最適化した大規模言語モデル(LLM)の共同開発と、さくらのクラウド基盤での提供を進める。
国産LLMの共同開発と商用化で国内完結の生成AI基盤
三者は、誤情報や制御不能な挙動など生成AIのリスクに対応するため、日本の文化や制度に適合したLLM(※)の共同開発を開始した。PFNは国産LLM「PLaMo 2.0」の後継となるLLM群をNICTと協力して構築し、独自の日本語データや合成学習データ、さらにNICTの収集したウェブページやインストラクションデータを組み合わせることで、高度な日本語性能を実現するとしている。
さくらインターネットは、自社の「さくらの生成AIプラットフォーム」で共同開発モデルを提供し、利用者がクラウドからアプリケーションまで完全に国内で完結する生成AIを利用できる環境を整備する。
さらに、700億ページ超の日本語ウェブデータを活用し、複数のAIを組み合わせた「AI複合体」の開発を進める。生成結果は動的評価基盤で検証し、文化的適合性や誤出力(ハルシネーション)の低減につなげる仕組みだ。
また、開発したLLMはプラットフォーム上でサービス化され、NICTのAI評価基盤の商用化に向けた実証にも用いられる。
国産生成AIの社会実装を通じ、国内の生産性向上と地域活性化を目指す方針である。
※LLM(大規模言語モデル):膨大なテキストデータを学習し、人間の言語を理解・生成するAIモデル。ChatGPTなどの生成AIの基盤技術として利用されている。
国産AI基盤の確立がもたらす利点と課題、将来展望
今回の取り組みは、日本のデジタル主権を確保する重要な一歩と言える。
具体的には、国内完結の生成AI基盤により機密性の高いデータを安心して扱える環境が整い、公共機関や企業の導入を後押しできるようになるだろう。
さらに、日本語性能を高めた国産LLMは、文化的背景や制度に配慮した応答が期待され、他国製モデルとの差別化要素になり得る。
メリットは大きい一方で、課題も少なくない。
世界のAI開発競争は激しく、継続的な投資や研究人材の確保が不可欠だ。特にGPUなど計算資源の確保や、長期的な資金調達の持続性が成否を左右すると考えられる。
また、国内完結の枠組みを強調するあまり、国際的なAI開発との互換性を損なう懸念も残る。
将来的には、国内で信頼性の高い生成AI基盤が確立されれば、産業界全体の生産性向上とともに、地方を含む多様な人材活用が進むことが期待される。
安全で文化に根差したAIの提供は、日本がグローバルなAI市場で独自の存在感を発揮する足掛かりとなるだろう。