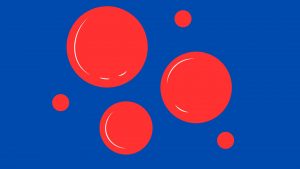HashPort、ステーブルコイン対応の後払い型クリプトクレジットカードをローンチ
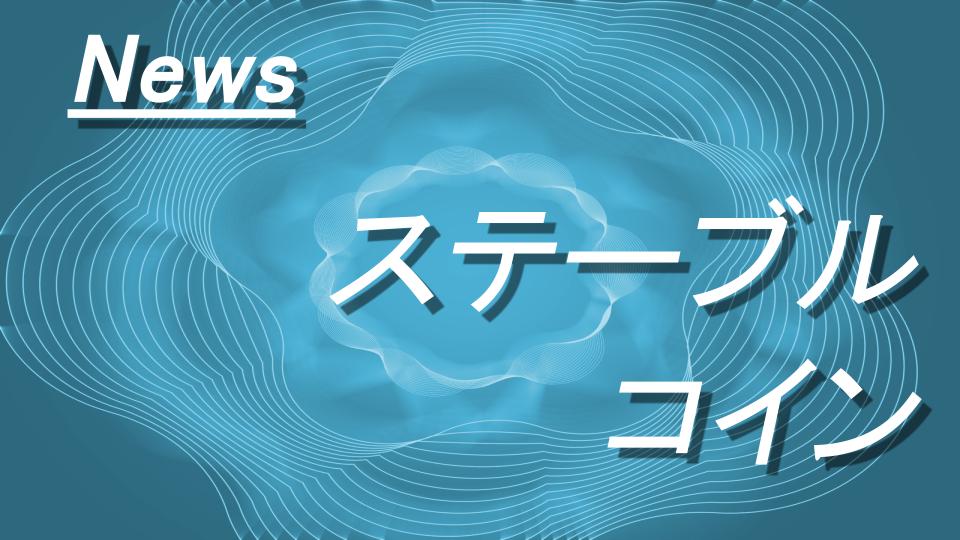
11月21日、ナッジ株式会社とHashPort株式会社は、日本初となる後払い型のクリプトクレジットカード「HashPortカード」の発行を開始した。
ステーブルコインによる決済と還元を実現し、デジタル資産の新たな決済インフラを構築することを目的としている。
ステーブルコインで決済・還元を実現 デジタル資産利用を日常化へ
21日、ナッジ株式会社とHashPort株式会社は、日本初となる後払い型のクリプトクレジットカード「HashPortカード」の発行を開始した。
「HashPortカード」は、HashPortが提供するウォレットアプリ「HashPort Wallet」と連携し、ウォレット内のデジタル資産をクレジットカード経由で利用できる仕組みだ。
決済額は従来のカードと同様に後払い方式を採用しており、事前に資産をロックする必要がない。
初期対応通貨は日本円ステーブルコイン(※)のJPYCで、将来的には複数のステーブルコインに対応する予定である。
特徴の一つは、決済額に応じた還元がJPYCで行われる点だ。
従来のポイント還元と異なり、ブロックチェーン上のトークンとして付与されることで、利用可能範囲が広がる点が利点とされる。
海外の一部クリプトカードのように独自トークンの価格変動によって実質的な還元率が下がるリスクもないとされる。
また、ナッジがカード発行とJPYC決済を担い、HashPortはウォレット連携による還元・特典の提供を担当する。
2026年初頭には、ウォレット内の残高からJPYCをガスレスで自動引き落とす仕組みが導入される予定であり、利用体験のさらなる向上が期待される。
さらに、2026年にはEIP-7702対応によるスマートウォレット化が予定されている。
※ステーブルコイン:米ドルや日本円などの法定通貨と価値を連動させた暗号資産。
「トークン経済圏」の足場に ステーブルコイン普及と規制整備が鍵
HashPortカードの登場は、デジタル資産を「投機」から「日常利用」へと拡張する動きの一環といえる。
法定通貨と連動するステーブルコインを用いることで、価格変動リスクを抑えつつブロックチェーン決済の利便性を享受できる点は強みだろう。
特にJPYCのような日本円建てのトークンは、国内の金融インフラとの親和性が高いため、Web3サービスとの連携拡大を後押しすると考えられる。
一方で、ステーブルコイン決済の普及には、利用者保護や資金決済法に基づく明確な運用ルールの整備が求められそうだ。
暗号資産取引所や金融機関との接続性を高めつつ、法的・技術的な安全性をどのように確保していくかが今後の焦点となるだろう。
スマートウォレット化により、ガスレス決済や自動引き落とし機能が実現すれば、ステーブルコインを基盤とするトークン経済圏が一層拡大する可能性がある。
日本発の後払い型クリプトカードが、デジタル金融の実利用フェーズを切り開く契機になるか、引き続き注目したい。
関連記事:
KDDIがHashPortと資本業務提携 万博実績活用し決済連携を拡大へ

JPYC、日本初の円建てステーブルコイン発行 Web3決済対応「JPYC EX」公開

EXPOウォレット刷新へ 「HashPort Wallet」に改称し、JPYCとガスレス対応