TISとJPYCが円建ステーブルコイン決済で協業発表 26年に新サービス提供へ
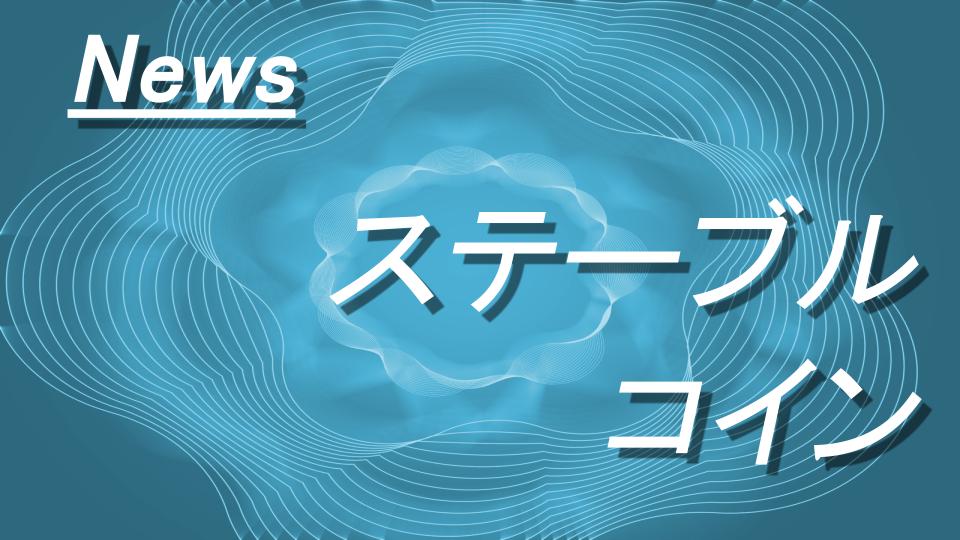
2025年11月14日、TISは、日本円建ステーブルコイン「JPYC」を活用した決済サービスの社会実装に向け、2025年10月31日にJPYC株式会社と基本合意書を締結したことを発表した。
両社は共同で新サービスの開発と普及を進め、2026年内の提供開始を目指すとしている。
TISとJPYC、円建ステーブルコイン決済で協業を開始
TISは2025年10月31日、JPYCと日本円建ステーブルコイン(※)の社会実装に向けた基本合意を結んだ。
TISが提供する「ステーブルコイン決済支援サービス」で、日本円と1:1で交換できる「JPYC」を取り扱うことで、事業者は新たな決済基盤を短期間かつ低コストで導入できるようになる。
2026年春から夏にかけて実施するPoCで実用性を検証し、同年内の正式提供を目指す計画だ。
背景には、日本国内でキャッシュレス化が進む一方、中小企業や国際取引では依然として現金を前提とした業務プロセスが残り、コストや時間のロスが目立ってきた点がある。
特に、訪日観光客向け決済や越境ECなどニーズの多様化が進む中、新しい決済手段の整備は喫緊の課題とされてきた。
JPYCは2025年8月に資金移動業者へ登録され、同年10月から国内唯一の円建ステーブルコインとして「JPYC」の発行を開始している。
また、TISは2025年2月からdouble jump.tokyoと協業し、ステーブルコイン決済に必要なシステム基盤の構築を進めてきた。
両社は2024年以降の情報交換を重ね、今回の協業に至った経緯がある。
※ステーブルコイン:法定通貨などの価値に連動して価格が安定するよう設計された暗号資産。送金の即時性や手数料の低さが特徴とされる。
円建ステーブルコイン普及に向けた課題と見通し
今回の協業によって、円建ステーブルコイン決済は企業や店舗にとって実用的な選択肢として広がっていく可能性がある。
ブロックチェーンを用いた直接送金型は専用端末を必要としないため、中小規模の事業者でも負担を抑えながら導入しやすくなると考えられる。
また、訪日客が保有するドル建ステーブルコインをそのまま使える仕組みが整えば、インバウンド需要の取り込みが加速する余地もありそうだ。
一方で、新しい操作フローやウォレット管理といったブロックチェーン特有の学習コストは課題としてなお残る。
ユーザー教育やサポート体制をどこまで整備できるかは、普及速度にも影響していきそうだ。
また、企業側でも既存システムとの連携や、内部統制の確保など、検討すべき技術的・運用的負荷が一定程度発生していく可能性も考えられる。
今後は、規制環境の整備状況や市場の受容度を踏まえつつ、円建ステーブルコインが新しい決済基盤として定着するかどうかが焦点になっていくだろう。
関連記事:
ヒノデテクノロジーズ、Plasmaと国内ステーブルコイン戦略パートナー契約

JPYC EXの口座開設が6000件を突破 円建てステーブルコインの利用が拡大
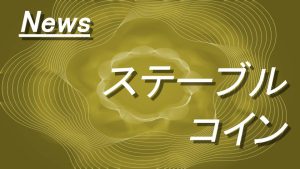
日本初ステーブルコインJPYCが発行額2億円を突破 正式リリースから18日で急拡大













