YouTube、AIによる無断顔使用を阻止する「類似性検出」機能を創設 クリエイターの顔が守られる時代へ
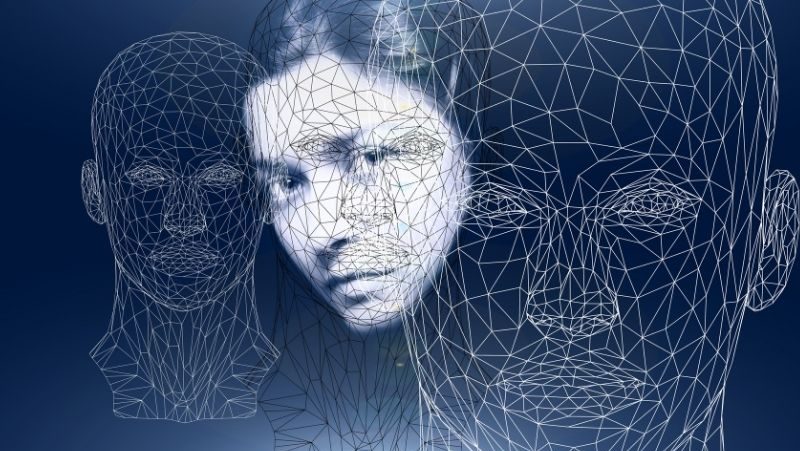
2025年10月21日、 YouTube は自身の顔が AI によって改変・生成された可能性のあるコンテンツを検出できる「類似性検出機能」を一部のクリエイターを対象に段階的に展開(ロールアウト)していることを発表した。
YouTubeが顔の「類似性検出」機能を一部のクリエイターに提供
YouTube は、著作権保護のために採用されてきた自動識別システム Content ID(※)と同様の仕組みを、人物の顔にも応用する類似性検出機能を展開した。
クリエイター自身が、政府機関発行の身分証明書と短い動画を YouTube Studio に登録することで、第三者が自身の顔を使って AI による改変・生成動画を投稿していないかを監視できるようになる。データは顔の類似検出用途のみに限定利用されるとしている。
また、本機能は顔だけでなく、「声」が AI によって改変または生成されたと思われる場合も検知可能だという。
登録後、検出された可能性のある動画が、YouTube Studioの「コンテンツ検出」>「類似性」タブに一覧表示され、問題のある動画に対して削除リクエストなどの対応を選択可能だ。
本機能は利用条件として、18歳以上かつ該当チャンネルの所有者または管理者であることが求められ、編集者権限のみでは設定できない。また、類似性検出を設定できるのは1チャンネルに限定されるという。
現在、この機能は実験的なベータ版として提供されている。
※Content ID:YouTube が著作権保護のために使用している、投稿動画の音声・映像を登録済みコンテンツと自動照合するシステム。
AI時代のクリエイター保護に向けた新段階 YouTubeの挑戦
YouTubeの「類似性検出」機能の導入は、生成AI時代におけるクリエイター保護の新たな柱となる可能性がある。
最大の利点は、顔や声といった個人の特徴を自動的に照合し、無断利用を早期に発見できる点だろう。
これにより、ディープフェイクによるなりすまし被害を未然に防ぎ、信頼性の高いクリエイター環境が形成されることが期待できる。
ブランドやアイデンティティを守る仕組みとして、企業コラボや広告案件の安心感も高まるだろう。
一方で、AIによる誤検出は避けられない課題となりそうだ。
正規の出演映像やコラボ動画まで「類似」と判定されるケースが生じれば、申請手続きの混乱や表現の自由をめぐる議論を招く可能性がある。
また、顔データや声紋といったセンシティブ情報を登録することへの心理的抵抗も残る。
今後は、こうしたリスクを最小化しながら制度を成熟させられるかが焦点となるだろう。
精度の高い検出アルゴリズムの改良と透明な運用ルールの整備が進めば、YouTubeは「コンテンツの真実性」を担保する国際的な基準を牽引する存在となるかもしれない。
逆に、運用の硬直化が続けば、クリエイター離れを招く恐れもある。
今後数年は、透明性と自由のバランスを模索する試行期になるとみられる。
関連記事:
人気YouTuber「きまぐれクック」かたるAI偽動画 詐欺サイト誘導で被害も確認













