OpenSea、NFT特化から“オンチェーン全資産取引”プラットフォームへ転換
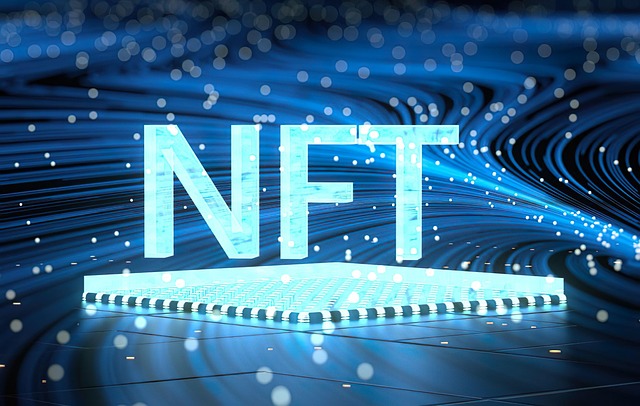
2025年10月17日、NFTマーケットプレイスのオープンシー(OpenSea)が、NFT特化型から暗号資産全般を扱うオンチェーン取引プラットフォームへと事業転換を進めていることが明らかになった。
同社共同創業者兼CEOのデヴィン・フィンザー氏がX上で発表した。
NFTから脱却し包括的取引プラットフォームへ再出発
オープンシーは2021年のNFTブーム期、世界最大級のNFTマーケットプレイスとして名を馳せた。
アーティストやコレクターがデジタルアートを取引し、NFT市場を牽引したが、ブーム後の市場低迷に伴い、取引量は減少した。
今回の方針転換は、事業の再活性化を狙った戦略的な一手とみられる。
フィンザー氏の投稿によると、直近の月間取引高は26億ドル(約3,900億円)を超え、そのうち90%以上がファンジブルトークン(FT ※)によるものだという。
「NFTマーケットプレイスから、全てを取引できる場所へと進化していく」と述べ、従来のNFT中心モデルを脱却する姿勢を鮮明にした。
さらに、2026年第1四半期(Q1)にオープンシー財団(OpenSea Foundation)を通じて新トークン「SEA」を発行する計画を発表。
供給量の50%がコミュニティに配分され、初回クレーム時に半数以上が配布される見通しだ。
ローンチ時収益の50%をSEA買い戻しに充て、プラットフォーム内でのステーキング機能も提供する予定とされる。
同社は現在、イーサリアム、ソラナ、ベースなど22のブロックチェーンに対応。
今後はモバイルアプリや無期限先物取引(パーペチュアル)機能も導入する計画で、NFTにとどまらず、オンチェーン資産取引のハブ化を進める方針を示している。
※ファンジブルトークン:互換性がある暗号資産。ビットコインやイーサリアムなどのように、単位ごとに価値が等しいトークン。
SEAトークンが鍵握る“再構築”の行方
オープンシーの事業転換は、NFT市場の飽和を背景に、より広範なオンチェーン経済圏で生き残りを図る戦略的な転機となるかもしれない。
最大のメリットは、NFTだけでなく暗号資産やデリバティブなど多様な資産を扱うことで、収益源を分散し、持続的な取引基盤を確立できる点だとみられる。
特に「SEA」トークンを中心としたガバナンス設計が機能すれば、ユーザー主導のエコシステム形成につながり、プラットフォームへの信頼性を高めるだろう。
一方で、暗号資産取引所としての再構築は容易ではないとみられる。
既存大手との競争だけでなく、トークンの設計次第では規制リスクや投資家保護の観点から監視が強まる可能性もある。
NFT特化のブランドイメージを転換しながら、新たなユーザー層をどう獲得するかも課題だろう。
今後は、DAO的運営と取引所機能の両立を通じ、オンチェーン経済の中核インフラとしての地位を築けるかが焦点となりそうだ。
SEAトークンが単なるインセンティブを超え、意思決定や利益分配に関わる「ガバナンストークン」として機能すれば、Web3時代の取引モデルを再定義する存在へと進化する可能性がある。
関連記事:
オープンシー、10月初旬にSEAトークン発行詳細発表 NFTリザーブ構想も始動












