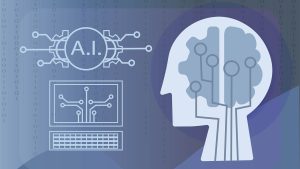AIロボットで学ぶプロクラミング 金沢の小学校で特別授業、児童が創意工夫で挑戦
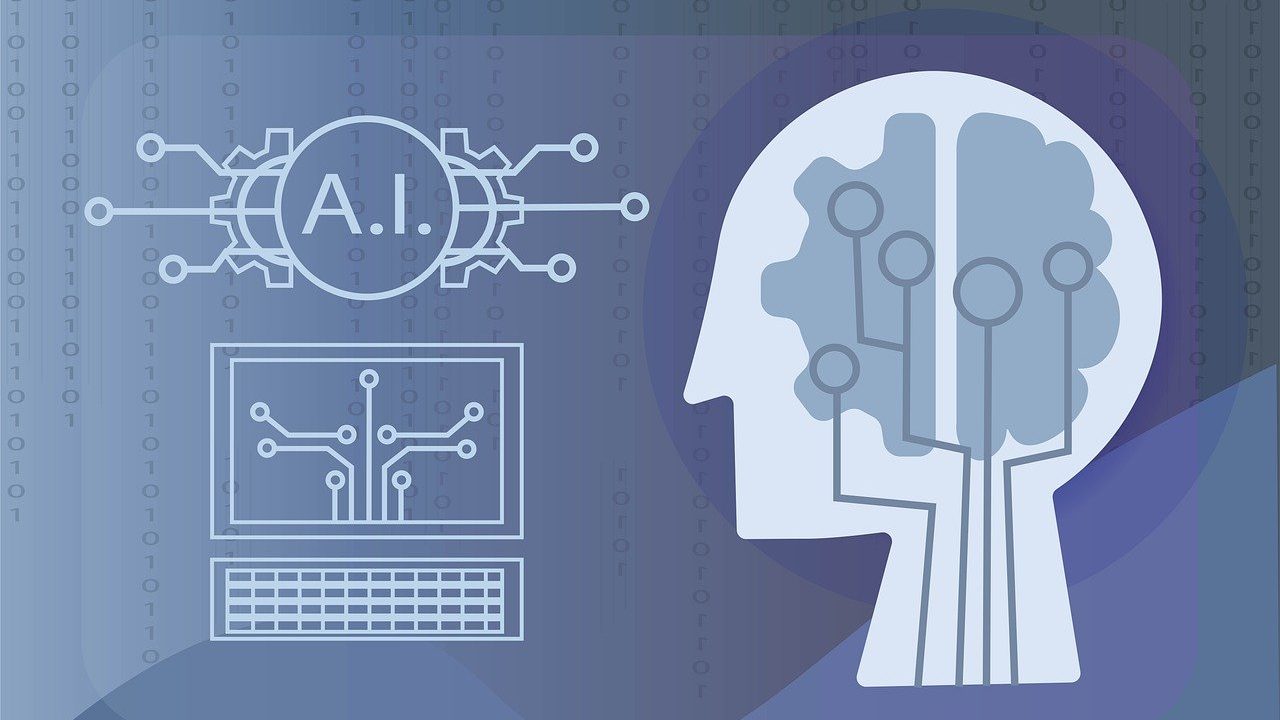
2025年10月10日、金沢大学附属小学校でAIロボット「Romi(ロミィ)」を活用した特別授業が行われた。
児童が自らプログラムを組み、会話を創り出す実践型学習に挑戦。試行錯誤を通じて「考える力」を育む取り組みである。
AIロボット「Romi」で学ぶ 児童が自ら会話を創造
金沢大学附属小学校で10日、MIXIが開発した会話型AIロボット「Romi(ロミィ)」を使ったプログラミング授業が実施された。
児童たちはタブレット端末で指示を入力し、ロボットと自然なやり取りを行う仕組みを自作した。
「好きな食べ物は?」「バナナが大好きだよ」といった会話から始まり、子どもたちはさらに高度な対話を目指してプログラムを改良。
なぞなぞを出題する会話プログラムを完成させた。
授業の狙いは、単なるコーディングスキルの習得ではなく、「どうしたらより良く動くか」を考え、試行錯誤する過程を体験することにある。
児童の一人は「(プログラミングを)いろいろ繋げないと完成しないとか、ルールを覚えるのが難しかったです」と話し、別の児童は「何でもわかるロミィになってほしい」と答えた。
MIXI Romi事業部の塩谷英右リーダーは「感情をもって会話をしてくれる存在を通して、プログラミングの楽しさやプログラミングのやり方、興味を持っていただいて、未来のエンジニアであったり、そういった人たちに育ってくれればいい」と語る。
AIと“共に考える”時代へ 教育の主役は子ども自身に
AI教育は今後、単なるプログラミングスキルの習得にとどまらず、「AIと協働して考える力」を育む方向へ進化していくとみられる。
Romiのような会話型ロボットは、子どもの思考をリアルタイムで可視化し、失敗を恐れず試行錯誤する姿勢を自然に引き出す効果が期待できる。
こうした学びの場は、創造性や課題発見力を中心に据えた新たな教育モデルを形成していく可能性が高い。
一方で、AIを導入する教育現場には、教師自身の理解促進や倫理的課題への対応も欠かせないと考えられる。
AIの判断をどこまで信頼し、どの段階で人が介入すべきか、教育の主体性をどう維持するかが今後の重要なテーマとなりそうだ。
さらに、生成AIが発想支援として機能するなかで、子どもの独自性をどう評価するかという新しい基準づくりも求められるだろう。
今回の授業で見られたように、AIを「教える存在」ではなく「共に考えるパートナー」として位置づける視点は、未来の教育を先取りする試みといえる。
こうした実践が全国へと広がれば、AIは知識を伝える道具から、思考を支える伴走者へと変貌していく可能性がありそうだ。
関連記事:
学研とMIXI、会話AIロボット「Romi」のコラボモデルをEDIX東京で初公開