リップル・DBS・フランクリンがMoU締結 米国債トークン化ファンド活用
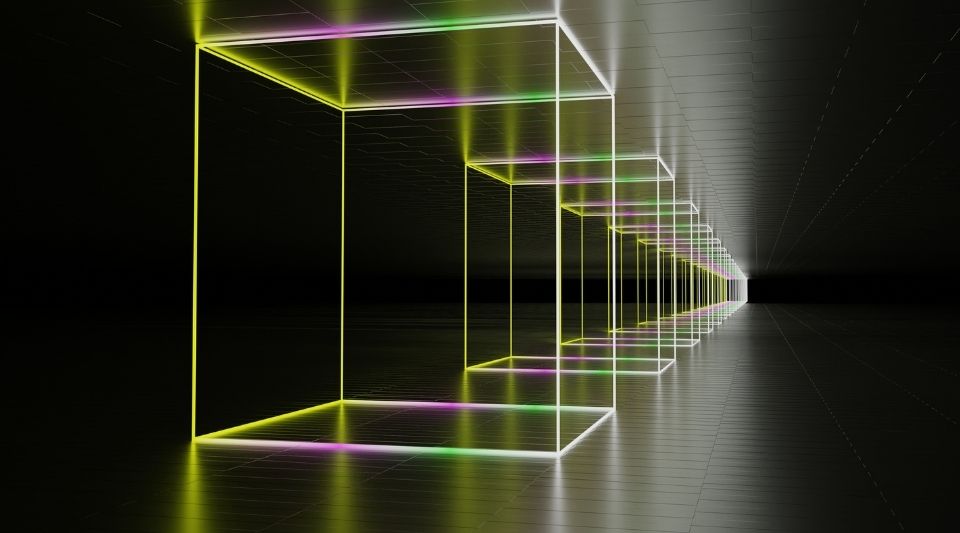
2025年9月18日、米リップル(Ripple)社はシンガポールのDBS銀行、米フランクリン・テンプルトンと覚書(MoU)を締結したと発表した。
米国債トークン化ファンドとステーブルコインを活用した取引・融資ソリューションの提供を目的とした国際的な連携である。
DBS取引所に米国債トークンとリップルUSD上場へ
今回のMoU(※1)により、まずDBSデジタル取引所(DDEx)において「sgBENJI」と「リップルUSD(RLUSD)」が上場する予定だ。
これにより投資家は市場変動時でも比較的安定した資産に即座にリバランスでき、利回りを得る選択肢が広がるとされる。
「sgBENJI」は、フランクリン・テンプルトンが運用する米国債トークン化(※2)ファンド「FOBXX(フランクリン・オンチェーン米国政府マネー・ファンド)」を裏付けとするトークンである。
一方の「RLUSD」は、ニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)の信託会社チャーターを取得したリップル社が発行する米ドル連動型ステーブルコインだ。
国際送金の効率化に特化しており、既にXRPレジャー(XRPL)とイーサリアム(Ethereum)上で発行されている。
DBSは次の段階として、「sgBENJI」を担保に銀行間のレポ取引(※3)や、サードパーティプラットフォームを通じた信用供与の仕組みを導入することを検討している。
これにより投資家は広範な流動性へのアクセスが可能となり、同時にDBSが担保を保有することで貸し手への信頼性を確保できる仕組みが構築される見込みだ。
さらにフランクリン・テンプルトンは「sgBENJI」をXRPレジャー上でもトークン化する計画を発表している。
これが実現すれば異なるブロックチェーン間での相互運用性が高まり、トークン化証券の取引や決済効率が一段と向上し、機関投資家のニーズに応える基盤となると期待される。
※1 MoU(覚書):契約締結前に当事者間で合意内容を確認する文書。法的拘束力は持たない場合が多い。
※2 トークン化:実物資産や金融商品をブロックチェーン上のデジタルトークンとして発行し、取引可能にする仕組み。
※3 レポ取引:債券を担保に現金を貸し借りする短期金融取引。流動性確保の手段として利用される。
伝統金融とブロックチェーンの融合が描く未来像
今後の展望として、リップル、DBS、フランクリン・テンプルトンによる覚書は、伝統金融とブロックチェーンの橋渡しとなる可能性を秘めている。
米国債を裏付けとするトークンと国際送金向けステーブルコインを組み合わせることで、投資家は市況変動時でも迅速に安定資産へ移行でき、資金調達やレポ取引の新たな選択肢が広がるだろう。
さらに「sgBENJI」が複数チェーン上で展開されれば、国境を越えた資金移動の効率性が一段と高まり、国際金融の基盤に変革をもたらす可能性がある。
一方で、規制当局の枠組み整備やコンプライアンス対応、チェーン間の技術的互換性といった課題は依然として大きいとみられる。
制度設計や市場受容性の進展が遅れれば普及は限定的にとどまる恐れもあるが、規制の明確化と標準化が進めば、トークン化資産は新たな信用インフラとして定着する見通しだ。
関連記事:リップルがRLUSDで2,500万ドル寄付 中小企業と退役軍人を支援
https://plus-web3.com/media/latestnews_1000_5309/












