東大とヌヴォトン、低電力エッジAI半導体の実用化へ前進
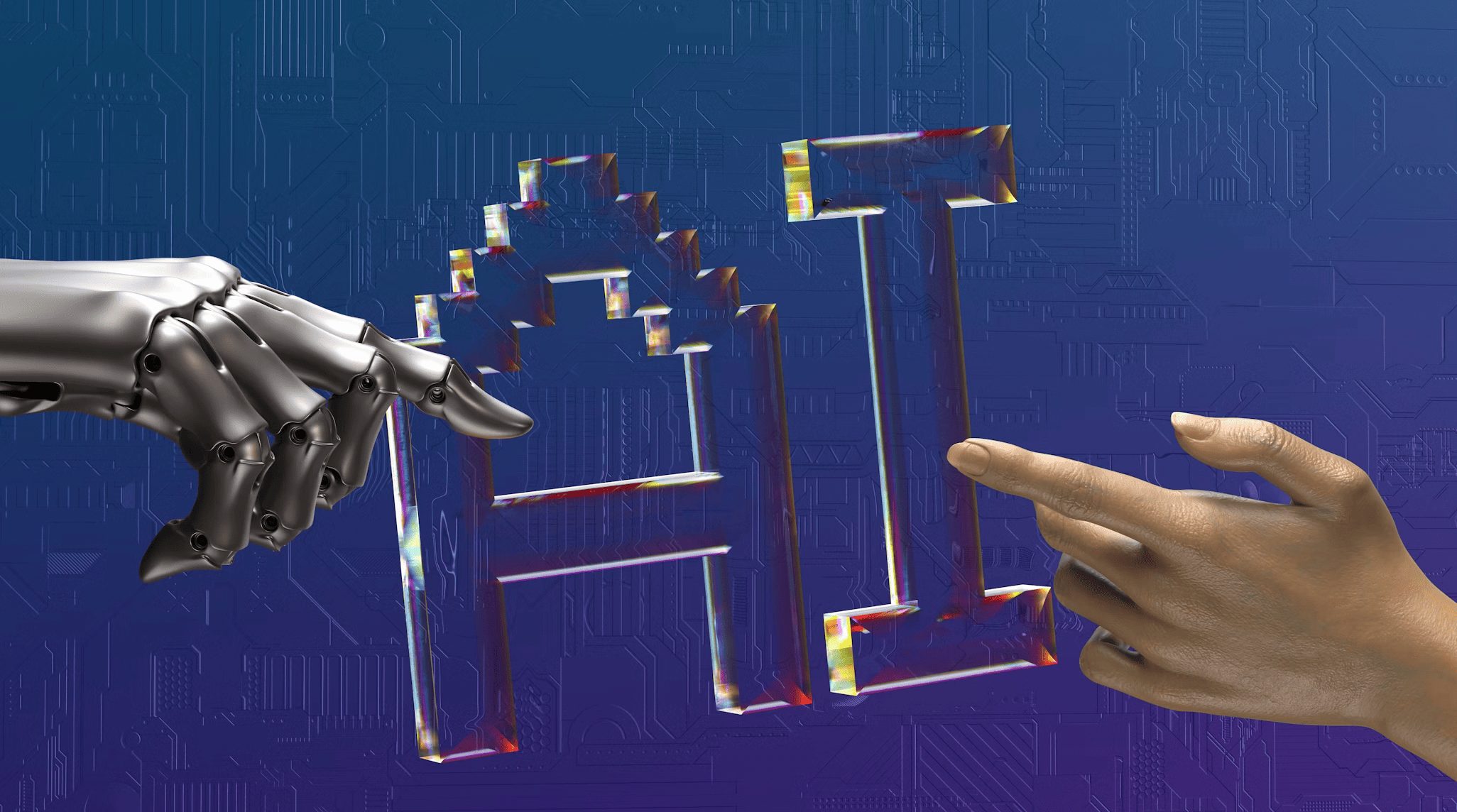
2025年9月11日、東京大学大学院工学系研究科とヌヴォトンテクノロジージャパンの研究チームは、低電力エッジAI半導体に用いるReRAM CiMで多値記憶と長期安定動作を両立させる技術を開発したと発表した。モバイルやヘルスケア分野での応用が期待される。
ReRAM CiMで大容量化と10年信頼性を同時達成
研究グループは、低電力AI半導体として注目される「ReRAM(※) CiM(Computation-in-Memory)」の大容量化と長期信頼性確保に成功した。
ReRAM CiMはデータ処理とメモリを一体化できるため、従来のコンピュータが抱える電力と速度のボトルネックを解消できるとされる。
特に、従来のGPUと比較して電力を10分の1以下に抑えられる可能性がある点が強みだ。
これまで、多値記憶方式を採用すれば大容量化は可能であったが、酸素欠陥の拡散によるデータエラーの発生が避けられず、10年規模の動作保証が困難とされてきた。
そこで今回の研究では、データ保持時間をモニターする回路を導入し、メモリ劣化に起因する推論精度の低下を補正する仕組みを実装した。
さらに、AIパラメータを上位ビットと下位ビットに分け、上位を2値メモリセルに、下位を多値セルに格納するハイブリッド構造を採用。
この工夫により、大容量化とともに10年間の高精度推論を可能にした。
研究成果は、モビリティ、ロボティクス、ヘルスケアなど、低電力半導体が求められる分野への導入が期待される。
※ReRAM(抵抗変化型RAM):電気的な抵抗変化を利用して情報を保持する不揮発性メモリ。
低電力AIが切り拓く応用 拡大期待と残る課題
今回の成果は、エッジAI半導体の低電力化を一段と進展させるものとなるだろう。
モバイル端末や医療機器といった電力制約の厳しい環境において、処理性能を維持しながら消費電力を削減できる点は大きなメリットになり得る。
特に、推論精度を10年間維持できる技術は、長期利用を前提とするインフラや産業用途でも強みを発揮すると期待できる。
一方で、課題も存在する。
多値記憶技術は製造コストや回路設計の複雑化を引き起こす可能性があり、量産化のハードルは依然として高いと予想できる。
さらに、実際のアプリケーションで安定的に稼働できるかについても、追加の実証が求められる可能性がある。
特にモビリティやロボティクス分野では、安全性や信頼性に直結することから、今後も慎重な評価が続くだろう。
それでも、ReRAM CiMの実用化が進めば、従来のGPU中心のアーキテクチャからの転換を促す契機となり得る。
AI処理の電力効率が大幅に向上すれば、エッジデバイスの普及やサービスの拡大を後押しし、次世代半導体市場の競争環境を変えるかもしれない。
東京大学大学院工学系研究科 東京大学工学部 プレスリリース:https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2025-09-11-002
関連記事:AIプロンプトの電力消費を公表 Google「Gemini」が示す環境負荷の実像
https://plus-web3.com/media/latestnews_1000_4919/












