Woltが東京で「デリバリーなのに店頭価格」導入 港区・新宿区・渋谷区の360店以上が参加
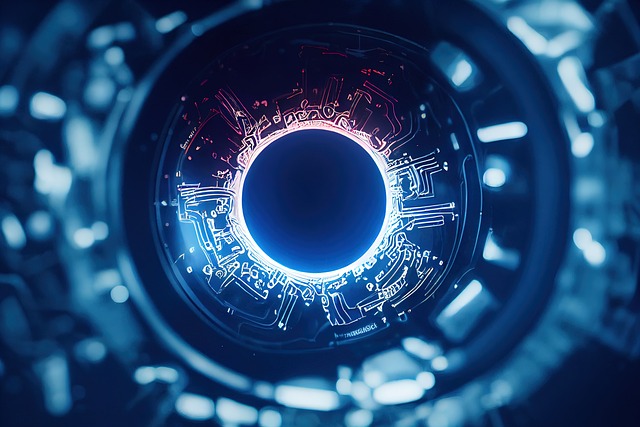
2025年9月2日、フードデリバリーサービス「Wolt」を運営するWolt Japanは、東京都内の一部エリアで「デリバリーなのに店頭価格」を開始した。
対象は港区・新宿区・渋谷区の加盟店で、開始時点で360店舗以上が参加している。
Wolt、東京都内で配送料別に店頭価格を実現
Wolt Japanは、同社が展開するデリバリーサービス「Wolt」において、商品価格を店頭と同じ水準にする新施策を打ち出した。
従来は、多くのデリバリーサービスが実店舗価格に上乗せした“デリバリー価格”を設定していたが、今回の取り組みではその差を解消し、ユーザーが店頭と同じ価格で商品を注文できるようになる。
対象店舗にはアプリ上で「店頭価格」と明記され、ユーザーが一目で確認できる仕様となる。
ただし、従来通りサービス料や配達料は別途発生する仕組みだ。
開始時点での参加店舗は360を超え、ハンバーガーチェーンの「シェイクシャック」やお好み焼きの「ぼてぢゅう」など、幅広いジャンルの飲食店が名を連ねる。
背景には、デリバリーを「価格が高い」として敬遠していたユーザーにも、気軽に利用してもらいたいという狙いがある。
Woltは2024年10月、広島県内の一部地域で同様の実証実験を実施していた。
その結果を受け、今回は人口密度が高く需要の大きい都心部での展開に踏み切ったとみられる。
「店頭価格」がデリバリー市場に投げかける波紋
今回の「店頭価格」導入は、今後のデリバリー市場に変化をもたらす可能性がある。
まず、消費者にとっては利用しやすさが増すことで裾野が広がり、気軽に試すユーザーやリピーターが増えると考えられる。
デリバリーを「高い」と感じていた層も取り込みやすくなり、サービス全体の利用頻度が押し上げられるシナリオが想定できる。
一方で課題も残る。従来の“デリバリー価格”は運営コストを補填する役割を果たしていたため、価格差を撤廃すれば利益率が圧迫される可能性がある。
特に小規模店舗では、売上増加と引き換えに採算が悪化する懸念が強まるだろう。
また、サービス料や配達料が別途発生する以上、「結局割高だ」と感じる利用者も出かねない。
期待と現実の差が広がれば逆効果となるリスクもある。
今後は、まず都心3区での利用動向や加盟店の反応を精査しつつ、他地域への拡大が検討されると見られる。
もし利用者増加と加盟店の収益確保が両立すれば、首都圏や他の大都市圏へ展開されるだろう。
成功事例となれば、競合他社も同様の施策を迫られ、業界全体で価格競争が一層激化する可能性がある。
Wolt プレスリリース:https://press.wolt.com/ja-JP/253749-wolt/
関連記事:Uber Eats、配達ロボを大阪で本格導入 ローソン商品を自動配送で受け取り可能に
https://plus-web3.com/media/latestnews_1000_3444/












