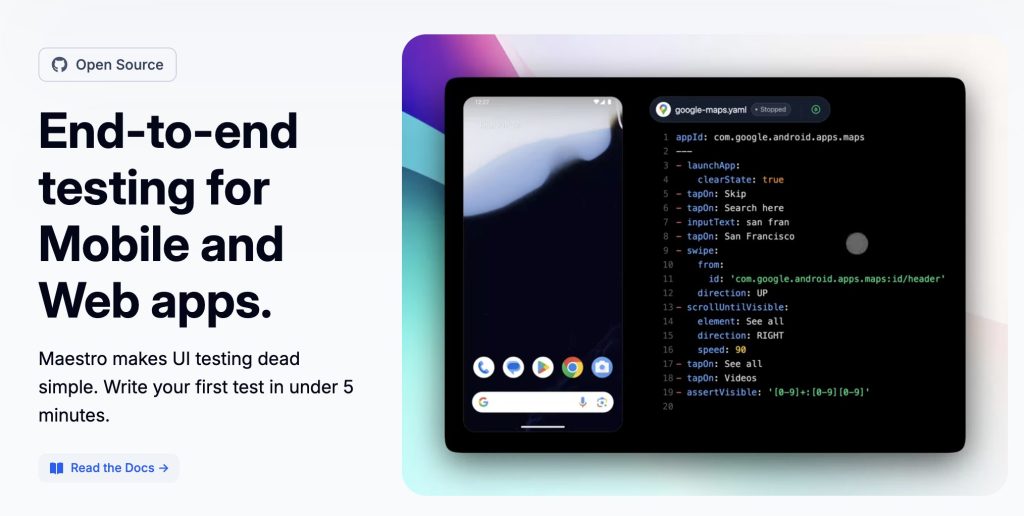ビザ、PYUSDとEURCなど追加 ステーブルコイン決済対応範囲を拡充

2025年7月31日、米決済大手ビザは、ステーブルコイン決済プラットフォームの対応範囲を拡充したと発表した。
新たに3種類のステーブルコインと2つのブロックチェーンを追加し、暗号資産によるグローバル決済インフラを強化する狙いがある。
ビザ、PYUSDやEURCなど3通貨・2ブロックチェーンに新対応
ビザは今回、ステーブルコイン決済の対象に、ペイパルが発行するPYUSD、パクソスのグローバルダラーUSDG、サークルのユーロ建てEURCの3通貨を新たに追加したと発表した。
これにより、既存のUSDCと合わせて4通貨をサポートする体制となる。
あわせて、利用可能なブロックチェーンにはステラとアバランチが加わり、従来対応していたイーサリアムおよびソラナと合わせて4つの主要ネットワークで運用可能となった。
今回の拡張により米ドル建てのみならず、ユーロ建てのステーブルコインによる決済も可能となり、パートナー企業の決済手段の柔軟性が大きく向上するとしている。
これまで25以上の法定通貨に対応してきたビザにとって、暗号資産との統合は決済多様化の一環であり、クロスボーダー決済の高速化やコスト削減につながると見られている。
7月には、米国でステーブルコインの発行と運用ルールを明確に定める「ジーニアス法(Genius Act)」が可決され、市場に一定の透明性と信頼性がもたらされた。
こうした背景のもと、ステーブルコイン市場は急速に拡大しており、現在の流通規模は約3,000億ドルにのぼる。
今後数年で2兆ドル超に達するという予測もあり、大手企業によるインフラ対応が進めば、商取引や国際送金の領域でも実用性が高まっていく可能性がある。
※ステーブルコイン:米ドルやユーロなどの法定通貨に価値が連動する暗号資産。
http://plus-web3.com/media/stablecoin/
ビザの対応拡大で加速する商用化 ステーブルコイン決済が現実解に
ビザがステーブルコイン決済の対応通貨およびブロックチェーンを拡充したことは、暗号資産の実用化に向けた現実的ステップになりそうだ。
最大のメリットは、対応通貨やチェーンの多様化によって、決済の柔軟性とアクセシビリティが格段に向上する点にある。
一方で、課題も残る。
米国では「ジーニアス法」の可決によって一定の法整備が進んだものの、他国との規制の足並みは依然として揃っていない。そのため、導入地域によっては、制度的不確実性や法的リスクを払拭しきれないだろう。
また、ステーブルコインの裏付け資産や発行主体への信頼性も、今後の普及に影響を及ぼすと考えられる。
今回のような決済インフラ拡充は、ステーブルコイン活用が「実験段階」から「商用化フェーズ」に移行するための要素となりそうだ。
仮に、ビザのような大手決済事業者が制度的裏付けと実需の双方を着実に積み上げていけば、ステーブルコイン決済は数年以内に電子マネーや既存のカード決済と並ぶ実用的な選択肢として、より広範に社会実装されていく可能性もあるだろう。