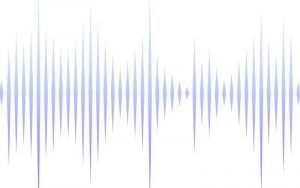西日本シティ銀行、生成AI活用の「HPナビゲーション」提供開始 顧客対応を内製で刷新
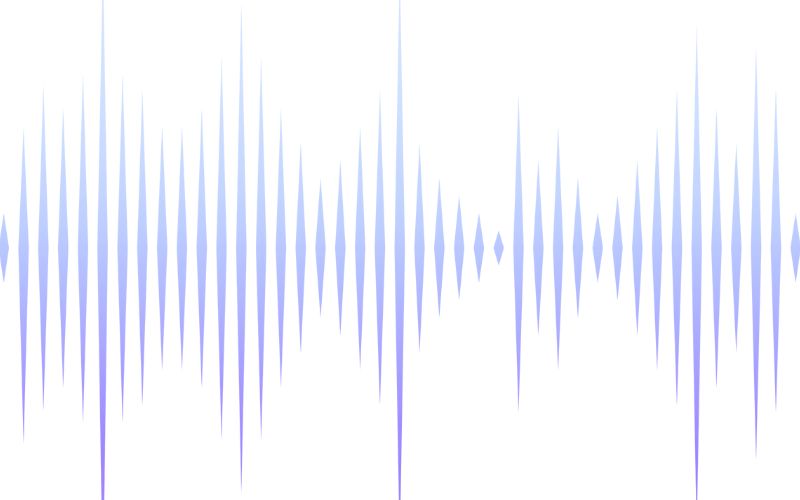
2025年11月5日、西日本シティ銀行は、生成AI技術を活用した内製開発サービス「HPナビゲーション」の提供を開始した。同行ホームページ上のチャット対応を刷新し、自然言語での質問に即応する仕組みを実現。顧客はより簡単かつ迅速に情報へアクセスできるようになった。
生成AIで顧客体験を再設計 内製開発で精度と操作性を両立
西日本シティ銀行は、従来の特化型AI(※1)によるチャットシステムを全面刷新し、生成AIを活用した新サービス「HPナビゲーション」を導入した。
これまで同行サイトでは、回答を得るまでに4つのステップ(質問入力、選択肢表示、選択、回答表示)を経由する必要があったが、新システムでは質問を入力するだけで即時に回答が表示される。さらに、回答画面には関連ページや問い合わせ先リンクも自動で提示され、ユーザーは求める情報に最短でたどり着けるようになった。
「HPナビゲーション」の導入により、話し言葉や自然文での質問にも柔軟に応答し、文脈を理解したうえで最適な回答を提示できるようになった。
たとえば「通帳を無くしました。どうすればいい?」といった質問にも即座に関連情報を提示するなど、従来よりも自然な対話体験を実現している。
さらに注目されるのは、同行がこのシステムを外部委託ではなく「内製」で構築した点である。同行は、生成AIの中核となる大規模言語モデル(LLM ※2)と検索拡張生成(RAG ※3)を組み合わせた内製開発を実現した。
今後も、各顧客に最適な情報や商品を提示する“One to One ソリューション”の提供を目指すという。
※1 特化型AI:特定業務に特化し、定義済みの目的に沿って分析や予測を行うAI。
※2 LLM(大規模言語モデル):膨大なテキストを学習し、人間のように自然な文章を理解・生成するAI。
※3 RAG(検索拡張生成):AIが回答を生成する前に関連情報を検索し、それをもとに正確な回答を生成する技術。
銀行DXの新たな潮流 生成AIが顧客接点の主軸に
「HPナビゲーション」の導入は、金融業界における生成AI活用の新たなモデルケースと言える。
最大のメリットは、顧客対応のスピードと正確性の向上だ。これまで人手や定型AIでは限界があった多様な質問に対し、生成AIが即時に最適解を導き出すことで、窓口やコールセンターへの負担を軽減できる。顧客は自然な対話で情報を得られるため、利便性が大幅に向上すると考えられる。
一方で、生成AI特有のリスクも存在する。誤情報の生成や、文脈を誤解した回答が出る可能性がある点は無視できない。
加えて、AIが参照するデータの安全性や更新頻度の管理も重要で、内製ゆえに人材育成と継続的な運用コストがのしかかるだろう。技術導入そのものが目的化すれば、ユーザー体験の一貫性を損ねる危険もある。
利便性と信頼性の両立こそが、今後の鍵となる。
今後、他行でも顧客接点の効率化や人員配置の最適化を目的とした生成AI活用が広がる可能性がある。特に、問い合わせ対応や商品説明など、繰り返し業務の多い領域での導入効果は大きいとみられる。
西日本シティ銀行の内製アプローチは、地方銀行におけるデジタル自立のモデルケースとして注目を集めそうだ。
関連記事:
ソニー銀行と富士通、生成AIで勘定系開発を効率化へ AIドリブンな金融システム構築に着手

京都銀行、生成AIでドキュメント検索を効率化 年間8,000時間の工数削減へ