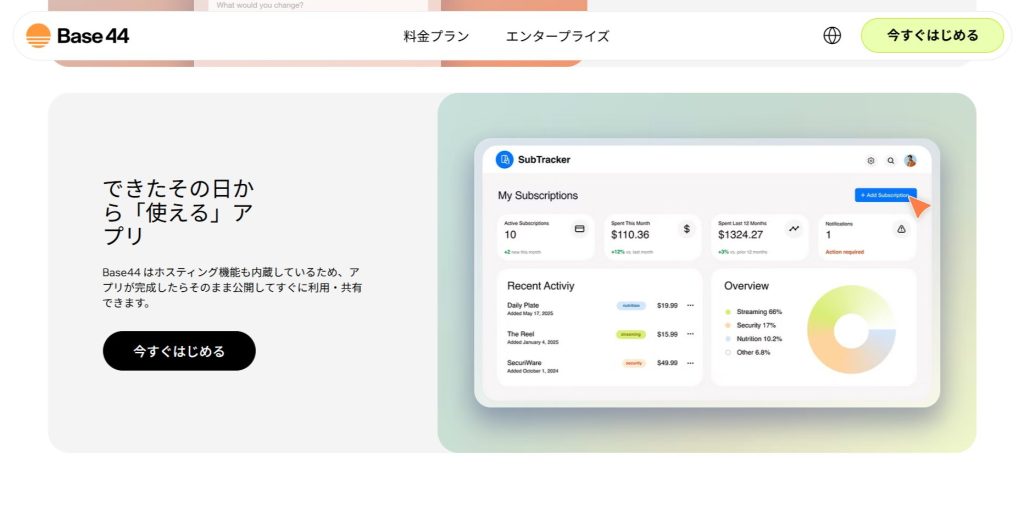堺市がAI食事管理アプリ「あすけん」導入 全国初、中学の健康教育にAI活用

大阪府堺市は、2025年11月1日にAI食事管理アプリ「あすけん」を市立中学校43校の約2万人に導入すると、同年10月23日に発表した。開発元の株式会社askenと連携し、生徒の栄養意識向上と生活習慣改善を目指す。
AIで食生活を「見える化」 堺市立中43校に「あすけん」導入
堺市教育委員会はAI食事管理アプリ「あすけん」を市立中学校43校に導入し、約2万人の生徒が11月1日から利用を開始する。中学校に導入されるのは全国初の事例となる。
アプリでは食事の写真やバーコードを読み取るだけでカロリー・栄養素が自動計算され、摂取状況をグラフ化して可視化できる。
今回導入される「学校教育向けバージョン」は、中学生の成長に合わせた栄養基準を設定し、学校給食の献立データが事前登録されている点が特徴だ。
授業中にパソコンから利用できるほか、家庭のスマートフォンでも同じアカウントで操作でき、学校と家庭の両面で食育を支援する。
堺市が導入を決めた背景には、子どもの朝食欠食や偏食の増加がある。農林水産省の調査によると、2023年度の中学生の朝食欠食率は8.7%と、2019年度の6.9%から上昇している。
開発元であるaskenは、グループ会社であるジーエスエフが堺市内の学校給食センター運営を担っている実績を持つ。その関係性を活かし、食育推進と健康支援を目的とした施策を市に提案。堺市は「あすけん」の導入に踏み切った。
10月にはトライアル授業も行われ、生徒からは「食事のことを前より気にするようになった」「食事の栄養バランスを考えようと思った」などの反応が寄せられているという。
AI食育がもたらす意識変化と課題 全国展開の可能性も
AIによる食事管理は、従来の「栄養指導」を一方向的な教育から双方向的な“体験型食育”へと進化させる可能性を持っている。
生徒自身が数値を見ながら栄養を学ぶ仕組みは、主体的な健康管理の第一歩となるだろう。栄養教諭にとっても、AIの解析結果をもとに生徒一人ひとりへ的確な助言を行える点で業務負担の軽減につながる。
一方、懸念点も存在する。デジタルツールに馴染みの薄い家庭では利用が定着しにくく、家庭環境による「食育格差」が広がる恐れがある。
また、アプリ内データの扱いには慎重さが求められ、個人情報保護や匿名化の運用ルールをいかに整備するかが課題となりうる。
それでも、中学校の教育現場でAIを使った健康支援を行う堺市の事例は、他自治体へ波及する可能性がある。AIが生徒の食生活を“見守る”時代は、すでに現実のものとなりつつあるといえるかもしれない。