京王線車内に「偽QRコード」貼付 電通大が注意喚起、悪意ある誘導の可能性

2025年10月21日、東京都調布市の電気通信大学は、京王線車内広告に同大と無関係の「偽QRコード」が貼りつけられる事案が発生したと発表した。偽コードを読み込むと同大学とは無関係の外部サイトへ誘導されることから、同大学は「二次元コードを見かけても読み込まないで」と警告している。
京王線広告に偽QRコード、外部サイト誘導が判明
電気通信大学によると、問題の広告は京王線車両の出入り口上部に掲示されていた横長の紙媒体だった。本来、同大学の公式広告にはQRコードは掲載されていないが、何者かがそれに似せたシールを上から貼りつけ、あたかも大学公式のリンクであるかのように見せかけていたという。
利用者の一人が不審に思い、SNS「X(旧ツイッター)」に状況を投稿したことで事態が発覚。大学関係者が投稿を確認し、21日朝に大学側へ報告した。電通大は直ちに京王電鉄へ連絡し、車内点検を実施した結果、1カ所の広告に偽コードが確認された。
他の車両には同様の貼付はなかったが、大学は警察へ相談し、被害の拡大防止に向けた対応を進めている。
同大学はX上で「本学の広告にQRコードは記載しておりません」と注意喚起を投稿。
広報担当者は「目的は分からないが、フィッシング詐欺(※)など悪質なケースも考えられる。読み込まないでほしい」と、利用者に警戒を求めているという。
※フィッシング詐欺:正規の企業や公的機関を装って偽サイトに誘導し、個人情報や認証情報を不正に取得する手口。メールやQRコードを悪用した事例が多い。
「公共広告の信頼」を狙う巧妙な偽装 拡大防止が急務
今回の事案は、公共空間に掲示される広告物の「信頼性」を悪用した新たな手口とみられる。
QRコードという仕組み自体には明確な利便性がある。利用者はスマートフォンをかざすだけで情報にアクセスでき、企業や大学にとっては印刷物のスペースを節約しつつ多様な情報を提供できる。広告の効果測定やデジタル連携も容易になる点は、現代社会において大きなメリットといえる。
しかし一方で、QRコードの構造的な弱点が今回のような悪用を招いた。
コードそのものが単なる画像情報であるため、見た目で正否を判断できない。公共広告や鉄道内ポスターといった「信頼されやすい媒体」に貼りつけられると、利用者は疑いを抱きにくく、フィッシングやマルウェア感染の被害につながる恐れがある。
加えて、こうした偽装行為は広告主や鉄道会社のブランドイメージにも傷をつけるリスクを伴う。利便性の裏側で、セキュリティと信頼性が常に揺らいでいる現実を示したといえる。
この事案を受け、鉄道会社や自治体、広告代理店には、ポスター掲示時のチェック体制の強化が求められる。特にQRコードを扱う際には、公式マークや電子署名といった、正規のコードであることを識別できる仕組みの導入が必要となるだろう。
QRコードの利便性を保持しつつ、信頼を担保する仕組みを社会全体で設計できるかが今後の課題である。
公共広告が悪意の温床ではなく、安全に情報を届ける媒体として機能し続けるためには、技術・運用・教育の三位一体の対策が不可欠だ。
関連記事:
PayPayがフィッシング詐欺へ3つの緊急対策を発表 スマートペイメント連携のQRコード廃止など
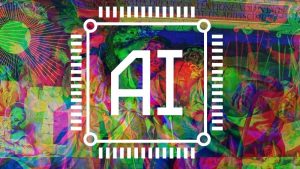
楽天証券でリアルタイムフィッシング詐欺発生 多要素認証を突破する新たなセキュリティ脅威













