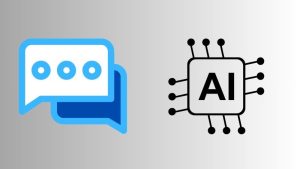ラクス、「楽楽自動応対」にAI返信生成を搭載 問い合わせ対応を自動化し業務効率化へ
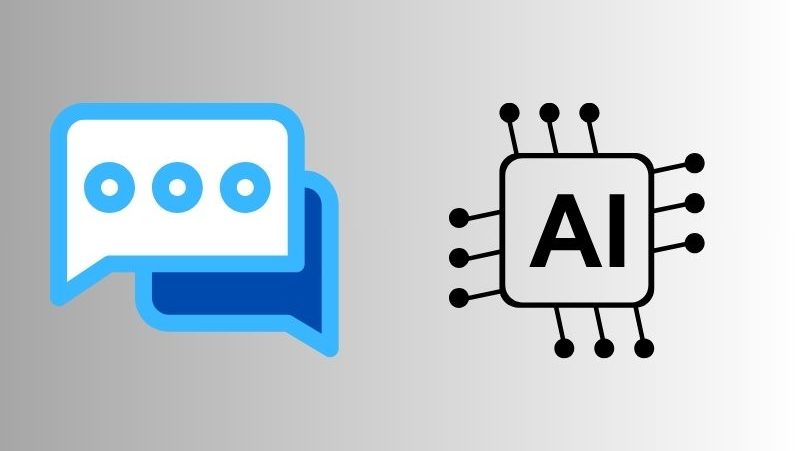
2025年10月21日、クラウドサービス事業を展開するラクスは、問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対(旧名称:メールディーラー)」に、AIがメール返信文案を自動生成する機能を搭載すると発表した。過去の応対履歴やFAQを基に返信内容を自動提案し、対応時間の短縮を図る。
「楽楽自動応対」、AIが返信メールを自動生成 ブランド統合で一体運用へ
ラクスが提供する「楽楽自動応対」は、企業の問い合わせ対応を支援するクラウド型システムである。今回新たに追加されたAI返信文自動生成機能では、過去のメール対応履歴やFAQデータを学習したAIが、問い合わせ内容に応じた返信文案を自動的に作成する。
この新機能は、7月に導入された「カスタム生成」に続く第2弾のAIエージェント機能にあたる。カスタム生成では返信の要点を入力する必要があったが、自動生成では入力すら不要になる。両機能とも標準搭載で、追加料金はかからない。AIが文面の初稿を担うことで、問い合わせ対応にかかる時間や工数の削減が期待される。
またラクスは同日、製品ブランドの統合方針も発表した。旧「メールディーラー」は「楽楽自動応対」へ改称し、メールマーケティングサービス「配配メール」も「楽楽メールマーケティング」に変更。両サービスを「楽楽クラウド」ブランドのもとに統一し、10月23日から順次適用を開始する。
AI応対がもたらす効率化と課題 品質維持が次の焦点に
AIがメール返信を自動生成する仕組みは、問い合わせ対応の効率化を大きく進める可能性がある。
メール対応は多くの企業で時間と人手を要する業務であり、文面の下書きをAIが担うことで、担当者は判断や確認といった付加価値業務に集中しやすくなる。
対応スピードの向上が顧客満足度の改善につながることも期待される。
一方で、自動生成された文面の精度や表現の適切さをどう担保するかが課題となる。
AIが誤った内容や不自然な表現を出力するリスクがあるため、一定の人手によるチェック体制を維持することが望ましい。
また、過去データに依存するAI学習の特性上、古い情報や限定的な事例が反映される可能性もあり、更新頻度や学習範囲の最適化が今後の運用を左右する要素となりそうだ。
ラクスが進める「楽楽クラウド」ブランド統合は、こうしたAI機能を複数の業務領域へ展開する基盤と位置づけられる。今後、営業支援やマーケティング領域にもAI応答が広がれば、企業内の情報共有やナレッジ活用の高度化が進む可能性がある。効率化と品質維持を両立する運用モデルをいかに確立できるかが、ラクスの成長における次の焦点となるだろう。
関連記事:
Perplexity、Max会員専用「Email Assistant」公開 AIがメール処理を自動化

マツリカのAI営業エージェント「DealAgent」、Outlook連携で直接メール送信