LINEヤフーと福岡市、生成AIでプラ分別支援の実証実験を開始
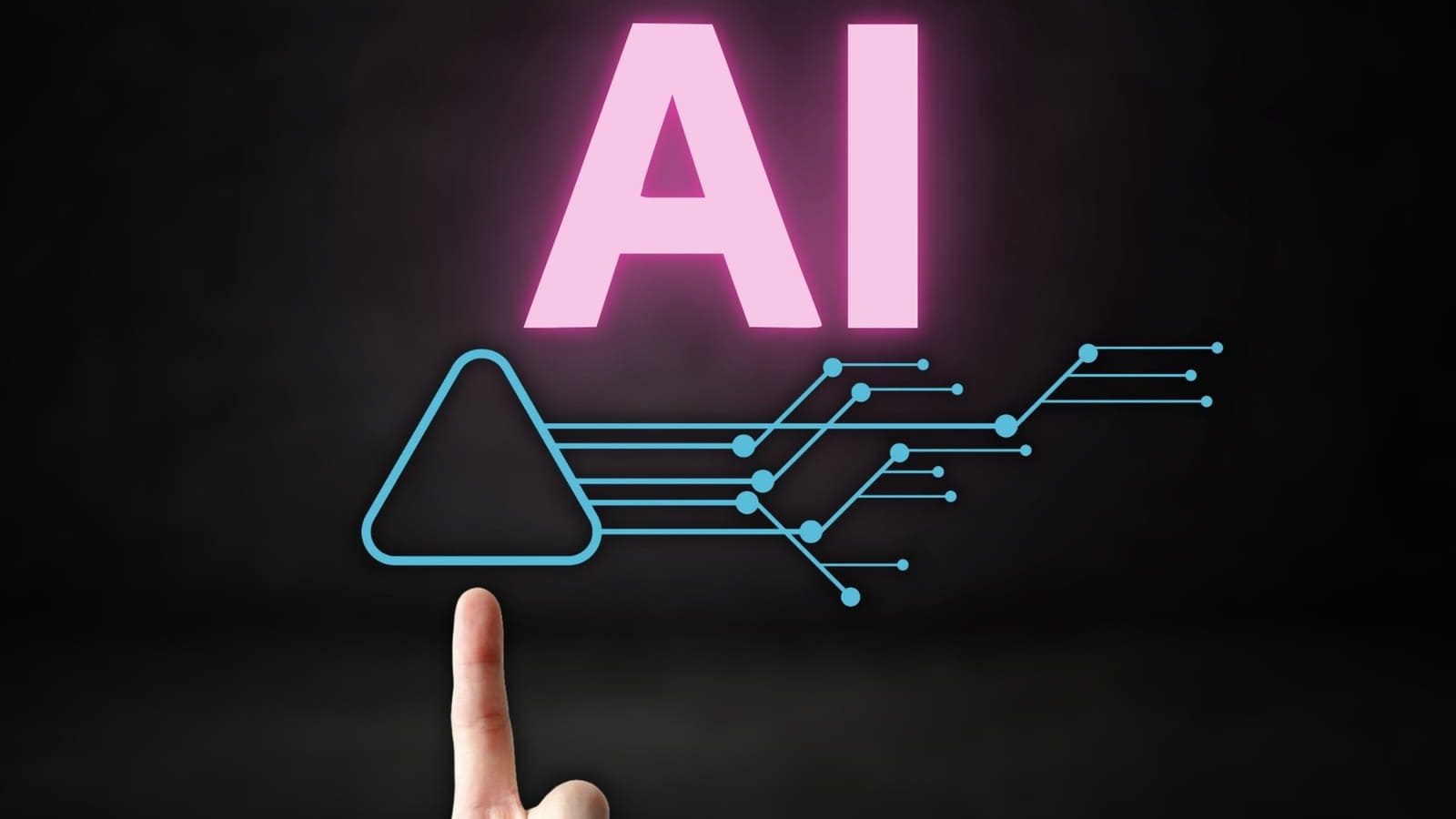
2025年10月15日、LINEヤフーコミュニケーションズは福岡市との連携により、生成AIを活用したプラスチック分別支援サービスのβ版を開発し、実証実験を開始すると発表した。
市民参加型で市民の分別行動の定着を目指す取り組みとなる。
福岡市LINE公式アカウント上でAIが即時分別判定
同サービスは、スマートフォンで品目を撮影するか名称を入力すると、生成AIが福岡市の分別基準に基づき即時判定し、出し方や洗浄の目安を案内する機能を持つ。
食品容器や金属混入品目も判定対象となり、モバイルバッテリーなど火災の危険がある品目には注意表記も付与する。
実証実験は2025年10月25日から2026年2月28日まで実施され、福岡市の環境フェスティバルや市内のプレ収集地区、公式Webページを通じて市民が参加できる。
評価ボタンやアンケートによりユーザーの満足度や使用感を収集し、AI精度やUIの改善を行う計画だ。
本取り組みの背景には、福岡市LINE公式アカウントの「ごみキーワード検索」が月平均3万回以上利用されており、分別迷いの解消ニーズが高い点がある。
また福岡市では、2027年2月からプラスチック分別収集が開始されるため、市民負担の軽減と行政対応の効率化が急務とされている。
福岡市環境局・藤本局長は、「プラスチックを資源物として回収し、新たなプラスチックの原料としてリサイクルすることで、現在の焼却処理する場合と比べて約5割のCO2削減効果を見込んでいます。(中略)サービスを活用していただくことで、すぐに自分で調べることができ、問い合わせする手間もなくなるなど、市民の皆さまの負担軽減に寄与することができると考えています。」と説明する。
一方、LINEヤフー・南方本部長も「AIが一次回答を担うサポーターとして機能することで、新しい分別区分の行動定着を図ります。」と述べた。
生成AI導入の利点と課題、今後の都市サービスへの波及
AIによる即時判定の導入は、分別に迷う品目への迅速な対応を可能にし、家庭での分別意識を高める効果が期待できる。加えて、行政側も問い合わせ対応の負担軽減や業務効率化といったメリットが見込まれる。
将来的には、プラスチック以外のごみ全般への分別支援や、他自治体への展開が進む可能性がある。こうした取り組みを通じて、自治体サービスにAIを組み込むことが、住民参加型のスマートシティ構築に寄与すると考えられる。
一方で、AIの判定精度や写真認識の限界により誤判定のリスクは残る。
市民からのフィードバックを適宜反映させ、精度向上や利便性の改善を継続する必要があるだろう。
また、データ収集段階での個人情報管理も重要な課題であり、安全かつ適切な運用体制を整備することが求められる。
総じて、今回の実証実験は市民参加型で環境意識を醸成する新たな試みといえる。
成果次第では、AIによる市民サポートが都市生活の一部として定着し、環境政策の効果測定や市民行動分析の高度化にもつながるかもしれない。












