オープンAI、ブロードコムと提携 初の内製AI半導体で供給網の主導権握る
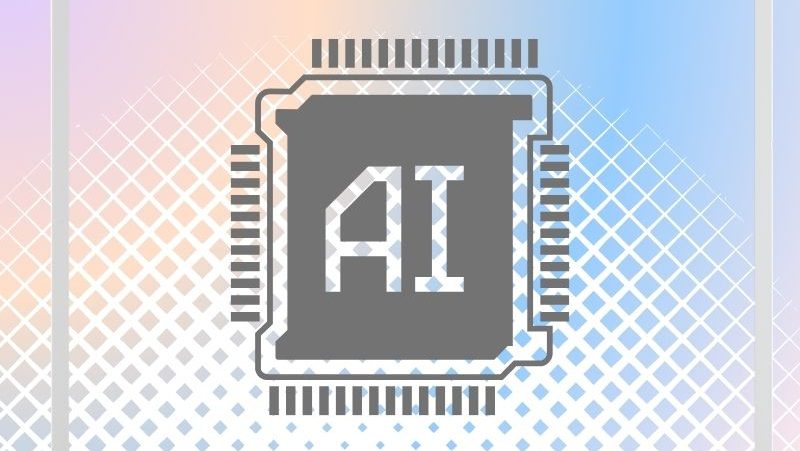
2025年10月13日、米オープンAIは半導体大手ブロードコムと提携し、初の内製AI半導体の生産に乗り出すと発表した。自社設計のカスタムチップをブロードコムが開発・製造する。
ブロードコムが開発支援 独自AIチップを量産化へ
オープンAIは今回の提携により、自社が設計したAI専用カスタムチップ(※)をブロードコムが開発し、2026年後半から量産を開始する。新チップの消費電力は10ギガワットに達し、米国内約800万世帯分の電力消費量に相当する規模となる。
サム・アルトマン最高経営責任者(CEO)は声明で「ブロードコムとの提携は、AIの潜在力を解き放つために必要なインフラの構築において重要なステップだ」と述べ、生成AIの開発と運用を支える基盤の自社確保を進める方針を示した。
最終的なシステムはブロードコムのネットワーク技術「イーサネット」を活用し、エヌビディアの「インフィニバンド」に対抗する構想である。
量産完了は2029年末を予定しており、長期的な開発投資が前提となる。
なお、今回の契約金額や資金調達の詳細は非公表である。
※カスタムチップ:特定の用途に最適化された半導体。AI処理などの計算を高速化し、汎用GPUより電力効率が高いのが特徴。
AI産業の主導権争いが加速 インフラ自立化の先にある課題
今回の提携は、オープンAIが「ソフトウェア企業」から「インフラを持つAI総合企業」へと進化する転換点といえる。
AIチップを内製化することで、外部供給に左右されない柔軟な開発体制を構築でき、演算コストの削減やエネルギー効率を最適化できると考えられる。AI開発を支える電力需要やクラウド使用料の高騰を抑制する可能性もある。
一方で、チップ開発は高リスク事業でもある。巨額の設備投資や製造工程の最適化には長期間を要し、設計ミスや歩留まりの低さが利益を圧迫するかもしれない。さらに、AIソフトウェア群との互換性確保や開発エコシステムの形成にも課題が残る。
市場では「今回の取引がこの分野でのエヌビディアの牙城を揺るがすことはない」との見方が支配的だが、オープンAIがハードウェア層を押さえることで、AI産業全体の競争軸は“モデル性能”から“計算基盤の自立性”へとシフトすると考えられる。
今後、生成AI時代の覇権争いはインフラ領域に広がるだろう。












