電通総研、生成AIで上流工程を半自動化 本格運用を開始し「Know Narrator」と連携へ
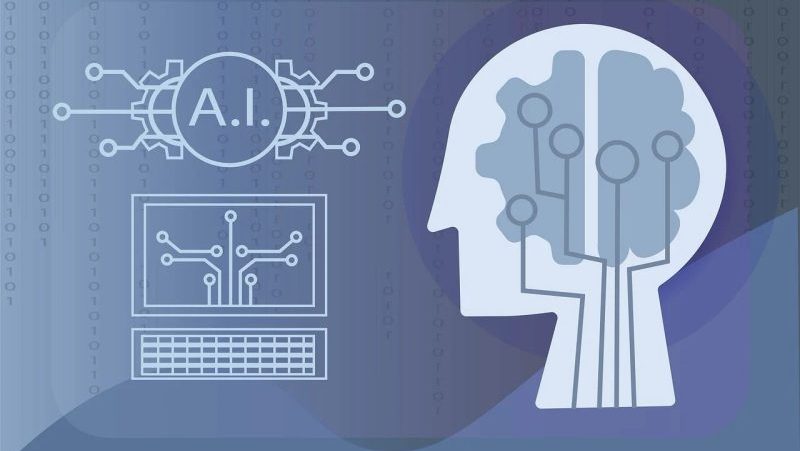
2025年10月9日、株式会社電通総研(東京都港区)は、生成AIを活用してシステム開発の上流工程を半自動化するAIエージェントを本格運用開始したと発表した。
社内開発のChatGPTソリューション「Know Narrator」との連携を進め、要件定義から設計までの効率化と品質向上を目指す。
電通総研、AIエージェントを本格運用開始 「Know Narrator」と連携し上流工程を半自動化
電通総研は、生成AIを用いてシステム開発の要件定義や基本設計、アーキテクチャ設計を半自動化するAIエージェントを開発し、本格運用を開始した。
2025年6月に行われた検証では、生産性が従来比で30%向上したと発表している。
このAIエージェントは、プロジェクトメンバーとの対話を通じて要求を整理・構造化し、要件定義書や設計書を自動生成する仕組みを備える。
社内データベースに設計情報を蓄積して再利用できるため、複数案件にわたるナレッジ共有を実現する。
また、仕様変更時にはAIが影響範囲を自動で特定し、修正案を提示することで、手動作業による設計ミスの発生を防ぐ。
これにより、成果物の整合性と品質を維持しながら開発全体の効率化を支援する。
さらに電通総研は、同社が開発する企業向けChatGPTソリューション「Know Narrator」とAIエージェントの連携を進める計画を示した。
2027年までに全ての新規開発案件で本技術の導入を目指すとしている。
AIによる上流工程改革が示す転換点 人材活用と品質維持の新バランス
今回のAIエージェント導入は、システム開発の上流工程における生産性と品質の両立を目指す動きの象徴である。
生成AIが要件整理や文書作成を担うことで、エンジニアは顧客との要件調整や構想設計など、より付加価値の高い業務に集中できる。
一方で、AIが出力する設計内容の妥当性を人間が精査する体制の構築は欠かせない。
生成結果の誤りや設計意図の解釈ミスを防ぐためには、AIの判断に依存しすぎない運用設計が求められるだろう。
AIが人間の設計思考を補完する新たな開発体制が確立すれば、企業システムの開発スピードと品質向上の両立に大きな一歩となる可能性がある。
また、AIによって設計プロセスが標準化されることで、熟練技術者の知見を若手人材へ継承しやすくなり、属人的な開発構造からの脱却も期待される。
さらに、こうした仕組みが産業全体に波及すれば、日本のソフトウェア開発の生産性を底上げする契機にもなり得る。
電通総研 プレスリリース:https://www.dentsusoken.com/news/release/2025/1009.html












