OpenAIのアルトマンCEO、「Sora 2」で権利者保護と収益分配の新方針を発表 日本の創作分野にも言及
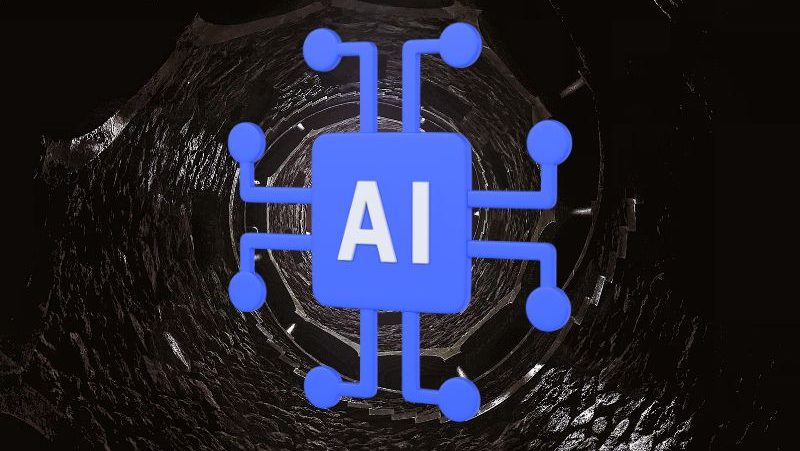
2025年10月4日、米OpenAIのサム・アルトマンCEOは自身のブログで、動画生成AI「Sora 2」に関する最初のアップデート方針を公開した。
権利者への制御権拡大と動画生成機能の収益化を同時に進める内容で、日本の創作文化にも特別な言及がなされた。
「Sora 2」で権利者の制御権と収益共有を同時に実現へ
アルトマンCEOは、Soraの運用ポリシーに2つの大きな変更を加えると明らかにした。
1つ目は、権利者が自身のキャラクターや作品をAI生成にどのように使うかを細かく指定できる「細分化されたコントロール機能」の導入である。
従来の「オプトインモデル(※)」を拡張し、権利者がキャラクターを使用しないよう設定することも可能になるという。
アルトマン氏は「多くの権利者から、この新たな『インタラクティブなファンフィクション』に非常に期待を寄せ、この新たな関与形態が彼らに大きな価値をもたらすと考えている声が寄せられている。ただし、自身のキャラクターの使用方法を指定する権限を保持したいと考えている」と説明。
OpenAIはすべての権利者に統一基準を適用しつつ、個別選択を尊重する方針を示した。
さらに、同氏は「特に、日本の驚くべき創造的な成果に敬意を表したいと思う。ユーザーと日本のコンテンツとの結びつきがどれほど深いかに感銘を受けている」と述べ、日本のアニメ・ゲーム分野がSoraの利用拡大において重要な役割を果たしていると評価した。
2つ目の変更は、動画生成の収益モデル導入である。
Soraの利用量が想定を上回ったことから、今後は動画生成を有料化し、収益の一部を権利者と共有する試みを始める。
具体的な分配設計は検討中だが、権利者が自らのキャラクター生成を許可した場合に報酬が発生する形を想定している。
アルトマン氏は「収益分配以上に、ユーザーと権利者の新たな関係性が価値を生む」とし、持続可能なエコシステム構築を目指す姿勢を示した。
※オプトインモデル:権利者が自ら同意した場合にのみ、データやキャラクターをAI生成に利用する方式。
生成AIの新たな倫理と経済圏 クリエイターとの共存が焦点か
Sora 2の方針転換は、生成AIが直面する「創造と権利の境界」を再定義する試みになり得る。
収益分配モデルは、AIプラットフォームと権利者の共栄構造を形成する可能性がある。
クリエイターがAI生成を通じて新たな収益源を得ることができれば、AIは単なる模倣ツールから“共創のパートナー”に進化する契機となるだろう。
権利者の制御権拡大により、法的リスクも軽減できると考えられるため、AI生成物の透明性を高める効果も期待できそうだ。
一方で、生成範囲の制限による表現の自由度低下も懸念される。
動画生成コストの上昇や小規模ユーザーの離脱といった課題も無視できないため、収益化による運営の持続性と、開放的な創作環境のバランスをどう取るかが今後の焦点になるだろう。
アルトマン氏は本件に関して、「ChatGPT初期のような高速な変化期」と述べているが、その言葉通り、Sora 2は試行錯誤を重ねながらAIとクリエイティブの共存モデルを模索していく段階にあると言える。
参考:Sora update #1
https://blog.samaltman.com/sora-update-number-1












