Google Arts & Culture、福田美術館と連携 名画にVeoで動きを加える新体験
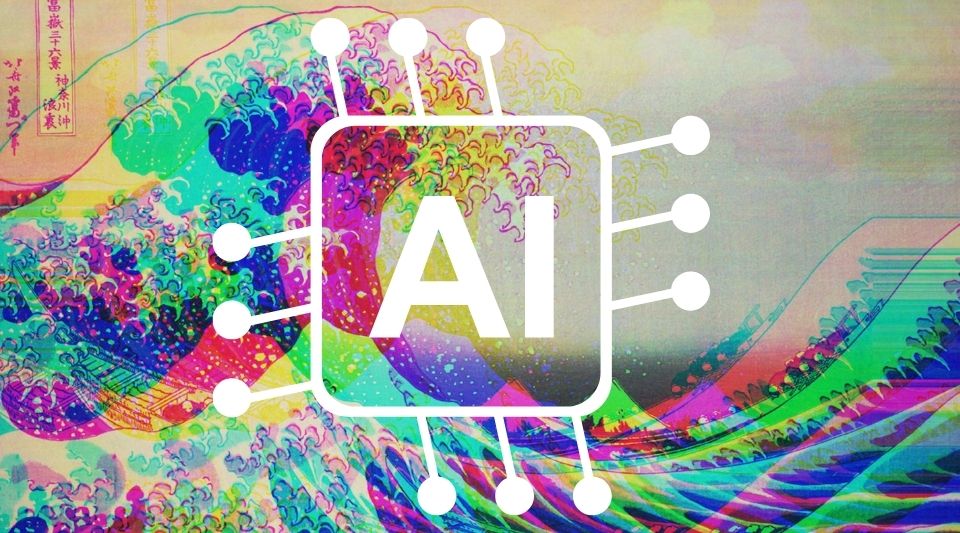
2025年9月24日、Google Arts & Cultureは京都の福田美術館と協力し、動画生成技術「Veo」を活用して名画に動きを与えるプロジェクト「Moving Paintings」を発表した。
日本発の取り組みとして、静止画の新しい鑑賞体験が国内外に広がる可能性がある。
Veoで24点の名画に動きを付与し公開
Google Arts & Cultureは、世界中のアートや文化をオンラインで広く公開することを使命とし、最新の生成AI技術を文化体験に導入してきた。
今回、同社は京都の福田美術館と連携し、動画生成技術「Veo(※)」を活用したプロジェクト「Moving Paintings」を立ち上げた。
対象は美術館のコレクションから選ばれた24点の名画である。
このプロジェクトの核心は、静止した絵画に動きを与えることで、鑑賞者と作品の間に新たな対話を生み出す点にある。
たとえば、歌川広重の「東海道五十三次之内 庄野 白雨」では、画中の雨や旅人の動きが再現される。
Veoは作品の構図や筆致に暗示された「動きの気配」を解析し、それを映像として生成する仕組みだ。
鑑賞者は「ARTISTIC」と「REALISTIC」の2モードを選択可能である。
前者はオリジナルの作風を踏襲し、画家の意図に沿った表現を再現する。
一方、後者は当時の景色を忠実に再構築し、実際に目にしたであろう光景を想起させる。
両モードは、作品を鑑賞する新たな切り口を提供するもので、単なる映像加工にとどまらない芸術的価値を目指している。
※Veo:Googleが開発する動画生成AI技術。静止画やテキスト入力をもとに高精細な映像を生成できる。
名画の新解釈を促進 世代や文化を超えた架け橋に
今回のプロジェクトは、美術鑑賞の裾野を広げる契機となる可能性が高い。
とりわけ若年層やデジタル世代にとって、動きのある映像は直感的に理解しやすく、名画との接点を増やす手段となり得る。
これまで静的な印象にとどまっていた作品に、物語性や没入感が加わることで、作品世界に一歩踏み込む体験が可能になると考えられる。
また、教育分野や観光産業への波及効果も想定される。
美術館に足を運ぶ動機づけとなるだけでなく、オンライン鑑賞を通じて、海外の鑑賞者にも日本美術の魅力を伝える役割を果たすだろう。
グローバルな文化交流の中で、日本発の美術館がテクノロジーと協業する意義は大きい。
もっとも、AIによる生成映像が「作家の意図を超える解釈」になる可能性も否定できない。
芸術と技術の境界をどのように扱うかは、今後議論を呼ぶことになるだろう。
ただし、福田美術館側副館長 竹本 理子氏も「当時の画家たちが思い描いたであろう光景を現代の私たちが体験できることは、誠に画期的なことです。」と言及しており、伝統と革新の調和を重視していることがうかがえる。
こうした取り組みは、文化資産を未来へ継承する新しいアプローチのひとつとして注目される。
アートとテクノロジーの融合が進む中、今回の事例はその可能性を具体的に示すものであり、今後の国際的なモデルケースとなる可能性がある。












