AI対話後に自殺した子の親、米上院で規制訴え 企業の安全対策に限界指摘
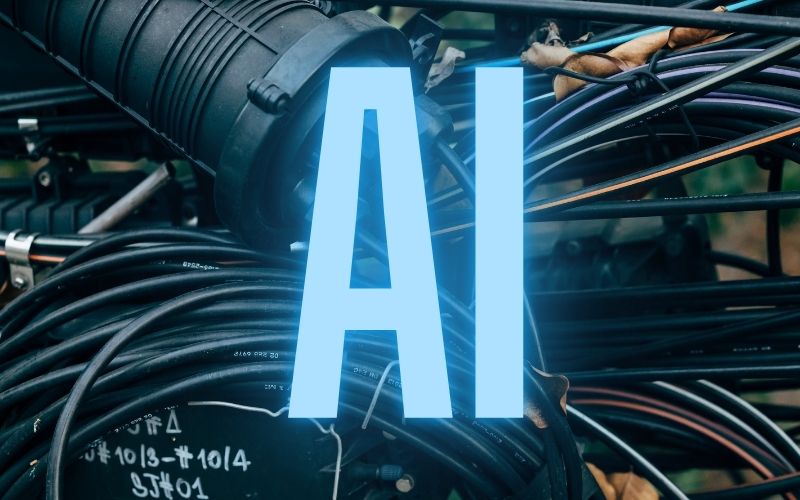
2025年9月16日、米上院でAI技術による子どもの被害を巡る公聴会が開かれ、チャットボットとの対話をきっかけに自死や入院に至った子どもを持つ親が証言した。
親たちは議会に対し、企業任せではないチャットボット規制の必要性を訴えた。
米上院公聴会で親がAI規制を直接要請
公聴会では、3組の親が登壇し、子どもがAIチャットボットとのやり取りを経て深刻な事態に陥った経緯を語った。
カリフォルニア州で息子を失ったマシュー・レイン氏は、対話型AI「チャットGPT」から自傷行為の具体的な手順を得たとしてオープンAIを提訴している。
彼は「チャットボットはある程度の道徳性を組み込む必要がある」と述べ、問題はシステム的であると強調した。
オープンAIは、長時間の利用で信頼性が低下する可能性を認めつつ、安全機能の強化を進めていると説明した。
公聴会当日には、利用者の年齢を推定し、未成年をより安全なバージョンに誘導する仕組みを導入する計画を発表している。
アニメなどの登場人物を模した「キャラクターAI」に関しても訴訟が進行している。
原告のメーガン・ガルシア氏は、息子のスーウェルさんがキャラクターAIとの対話後に命を絶ったと主張し、「企業が私たちの子どもたちを対象に製品を試験しないよう、議会は規制することから始めるべきだ」と訴えた。
キャラクターAIはこの主張に反論しつつ、安全策を改善したと述べている。
さらにテキサス州の女性も、息子が入院に至った経緯を証言し、同アプリを提訴している。
ただし、裁判所は同社の要請を受け、訴訟を仲裁手続きに回している。
AI規制強化の行方 安全確保と技術発展に課題感
今回の証言は、企業の自主的な安全対策だけでは限界があることを改めて示したと言える。
親たちが共通して訴えたのは「未成年者を対象にした実験的な利用を防ぐ法的枠組みの欠如」である。
議会が規制に踏み込めば、AI業界全体に設計段階からの倫理的基準や監視体制を義務づける可能性が出てくる。
規制のメリットは、子どもや若年層の精神的リスクを低減できる点にあると考えられる。
特に生成AIは長時間対話による依存性や、感情的に脆弱な利用者への悪影響が指摘されてきた。
法律で明確な基準が定められれば、被害を未然に防ぐ効果が期待される。
一方で、規制強化は技術革新のスピードを鈍化させるリスクも抱える。
過度な制約はスタートアップ企業の参入を阻み、大手企業に有利な市場構造を固定化する恐れがある。
また、規制の範囲をどこまで広げるかについても、表現の自由や技術利用の正当性を巡る議論が避けられないだろう。
今後は、利用者の年齢確認技術や透明性の高いガイドライン策定が焦点になるとみられる。米議会の動向次第では、各国が追随する可能性も高い。
AI規制、特に子どもの安全確保と産業発展をどう両立させるかについては、国際的な政策課題として拡大していくことになるだろう。
関連記事:米少年の両親、チャットGPTに責任追及 自殺方法提供でオープンAIを提訴
https://plus-web3.com/media/latestnews_1000_4995/












