東京都、地下空間浸水対策にAI導入 17年ぶりガイドライン改定で避難行動を明確化
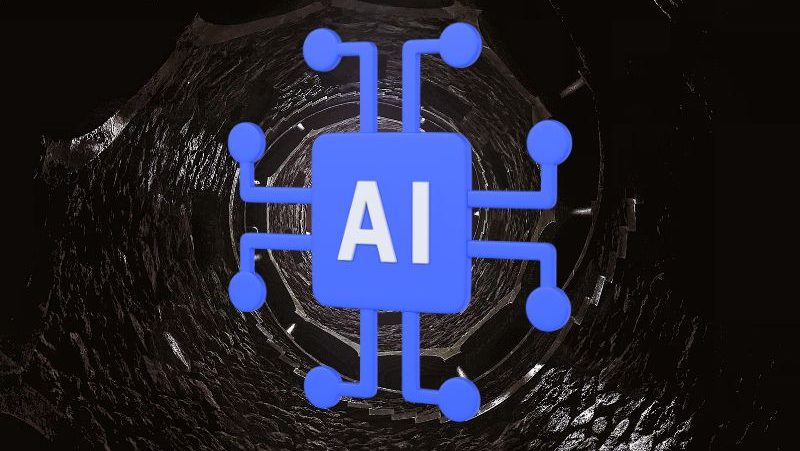
2025年9月9日、東京都は地下街や地下駐車場などの浸水リスクに対応するため、2008年以来17年ぶりに「地下空間浸水対策ガイドライン」を改定した。
AI技術を活用し、浸水リスクの予測や避難経路の提示を強化した点が特徴である。
AIで浸水リスクを判定 施設管理者の行動も明文化
東京都は、地下空間の浸水対策ガイドラインを全面的に見直した。
従来の予防策に加え、AI(人工知能)を用いたデータ解析を導入し、浸水リスクの高い出入り口や最適な避難経路を事前に把握できる仕組みを整えた。
これにより、止水板の設置や避難誘導をより正確に行うことが可能になることが期待される。
AIは、過去の被災事例や地形データを学習しており、数時間前から発災後に至るまでの行動計画を施設管理者に提示する。
そのほか、新ガイドラインには、情報共有の方法や避難誘導の手順などが明記され、担当者の役割がより明確化された。
今回の決定の背景には、地下空間の増加と複雑化がある。
2008年当時、都内の地下空間は約6万8000か所だったが、再開発により2023年には7万2000か所に拡大した。
地下街や駅が相互に接続するケースも増え、構造は非常に複雑になっている。
東京駅八重洲地下街だけでも1日約10万人が利用しており、災害時の迅速な対応が求められていた。
さらに、気候変動による豪雨の頻発も深刻だ。関東甲信地方では「1時間に50ミリ以上の降水」の発生回数が、20世紀末と比較して21世紀末には最大3.5倍に増えると予測されている。
こうした状況を踏まえ、都はAIを軸とした新たな浸水対策に踏み切った。
AI活用で迅速な避難誘導へ 精度と実効性に課題も
改定ガイドラインは、AIによるリスク分析を基盤に据えた点で画期的だ。
予測精度が高まれば、浸水発生前に的確な防止策を打ち出し、人的被害を抑制できる可能性がある。
施設管理者にとっても行動指針が具体化され、迷いなく対応できる利点があるだろう。
一方で、課題も残る。AIが提供するリスク判定は過去データやモデル精度に依存するため、想定外の豪雨や複雑な構造での浸水に対応できるかは不透明だ。
また、施設管理者が実際にシステムを理解し、避難誘導を確実に実行できるかも実効性を左右する要因となる。
東京都は今後、自治体や民間施設管理者と連携し、新ガイドラインの定着を図る方針を示している。
AI導入を契機に、都市の防災力を実質的に高められるかどうかが問われる局面にあると言える。












