テロ前兆をAIで把握へ 警察庁、SNS投稿を対象に実証実験開始
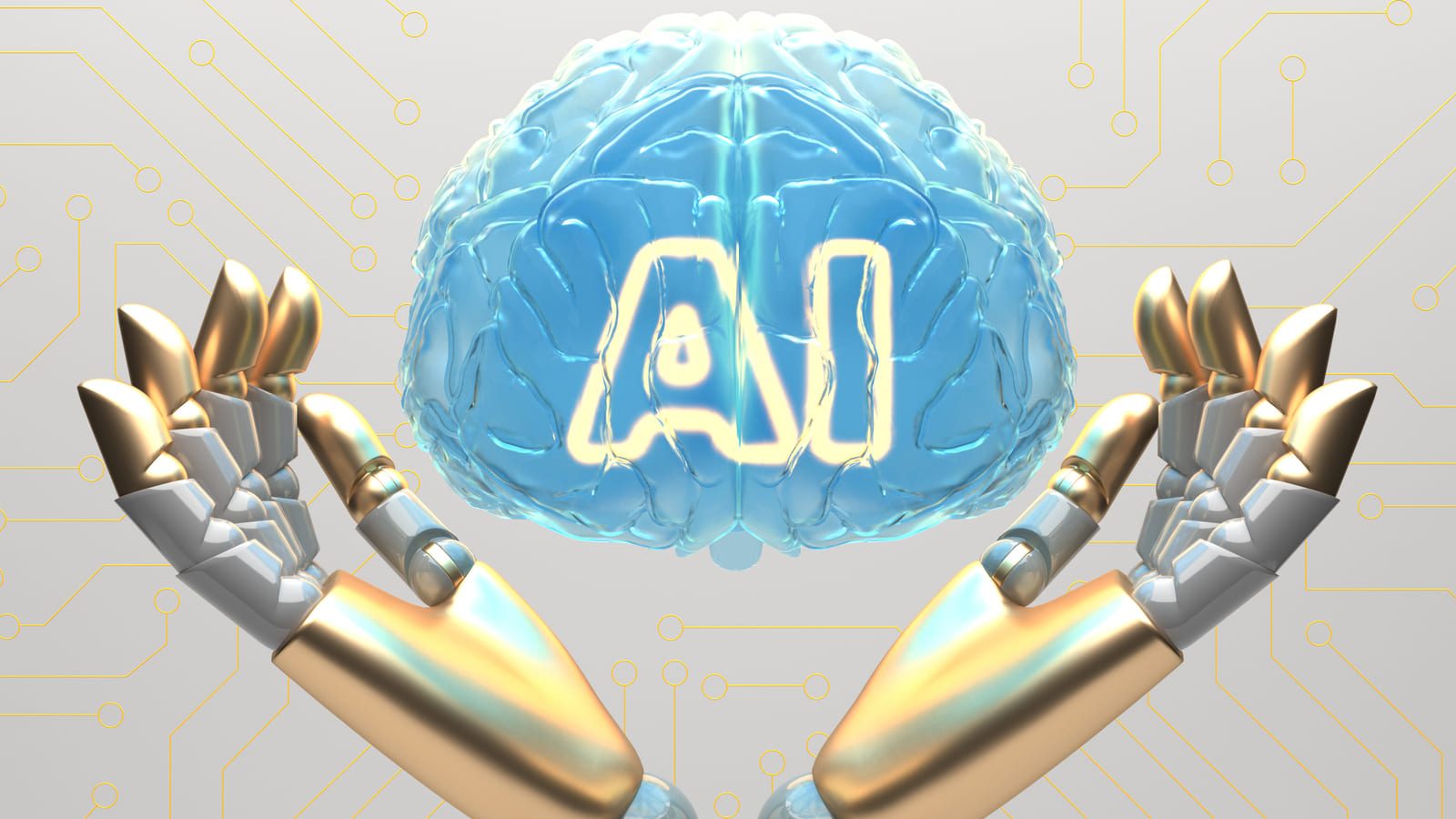
2025年9月10日、警察庁はSNS投稿をAIで解析し、テロの前兆を検知する実証実験を来年度から開始することが報じられた。
単独犯の潜在的脅威を対象に、投稿内容を危険度ごとに判定し、未然防止につなげる狙いがある。
警察庁、AIでSNS投稿を解析し危険度を判定
警察庁は、来年度予算の概算要求に4950万円を計上し、AIを活用したテロ防止の実証実験を実施する方針を明らかにしたという。
対象とするのは、特定の組織に属さず単独で攻撃を企図する「ローンオフェンダー」である。従来の捜査網では捕捉が難しい存在であり、SNS投稿の分析を通じて早期に兆候をつかむ狙いがある。
背景には、選挙や要人演説を狙った脅迫的な書き込みが後を絶たない現状がある。
2025年7月の参院選では、岸田文雄前首相の演説予定に対し「来たら殺す」と投稿する事例が確認され、警察が投稿者を特定して警告を行った。このような危険発言は1カ月間で約900件にのぼり、すべて人力で発見されていた。だが投稿量の膨大さから、現行体制には限界が指摘されている。
新たな仕組みでは、AIが「爆弾」「56す」「4ね」といった危険ワードを抽出し、過去の投稿傾向も含めて危険度を算定する。単なる悪ふざけと深刻な脅威を峻別することが不可欠であり、AIは投稿履歴をさかのぼってテロ称賛の有無を分析する。
最終的な対応は警察官が担い、摘発や警告に結び付ける運用を想定している。
AI警戒網がもたらす抑止効果と監視リスク
AIによる投稿解析は、従来の捜査力を補完し、迅速な危険検知を可能にする点で大きな意義を持つ。
従来の人力監視では見逃されていた投稿も早期に抽出でき、要人警護や公共空間の安全性を高める効果が期待される。特に単独犯による攻撃は予兆が小規模で見逃されやすいため、AIが早期警戒網を形成する意義は大きいといえる。抑止効果も期待でき、潜在的な犯行計画を思いとどまらせる可能性もある。
一方で、過剰な監視や誤検知のリスクは避けられない。
AIが危険度を誤って高く判定すれば、無実の一般市民が警告対象となり、表現の自由やプライバシーを侵害する恐れもある。
また、SNSでは偽アカウントや海外からの投稿も多く、精度の確保が課題となる。匿名性や越境的な利用が多いSNSでは、実効性や責任の所在も揺らぎやすい。
今後、AI制度の精度向上や倫理的ガイドラインの整備は、日本国内で進んでいくとみられる。その一方で、社会的議論は避けられず、「安全確保」と「自由の保障」をいかに両立させるかが大きな課題になるだろう。
導入が拡大すれば抑止力は確実に高まるが、過度の監視国家化を招かないための透明性と監視体制の監督が求められると考えられる。
関連記事:警察庁、トクリュウ摘発を強化 AIが犯罪相関図を描く
https://plus-web3.com/media/latestnews_1000_5015/












