米エヌビディア、生成AI特化チップ「ルービンCPX」発表 動画・ソフト制作を高速処理へ
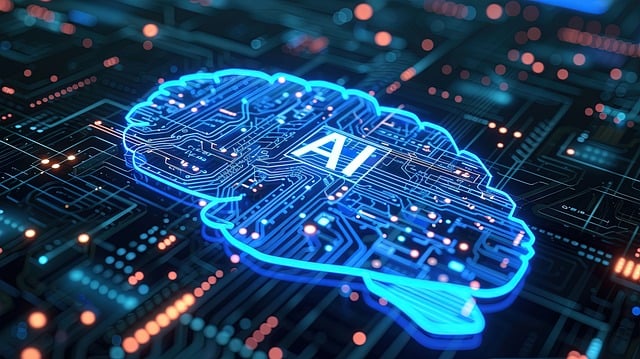
2025年9月9日、米半導体大手エヌビディアは、動画やソフトウエア生成などの高度な処理に対応する次世代AIチップ「ルービンCPX」を2026年末までに発売すると発表した。
新アーキテクチャである「ルービン」に基づき、従来のGPUでは難しかった大規模処理を統合的に実行可能にする。
動画・ソフト生成に特化 「ルービン」アーキテクチャで性能強化
エヌビディアは生成AIによる動画編集やソフトウェア開発などの重負荷処理向けに新たなAIチップ「ルービンCPX」を発表した。
これは同社が開発する「ルービン」アーキテクチャを採用した初の製品群の一つであり、AIモデルによる膨大なデータトークンを扱う処理にも対応できる。
従来の画像処理用GPUでは、1時間分の動画生成に必要なトークン(最大100万トークン)を扱うことは困難だった。これに対し「ルービンCPX」は、動画デコード・エンコード・推論といった工程を新しいチップに統合することで、処理速度と安定性を高めている。
AIの活用範囲が拡大し、バイブ・コーディング(※)などの複雑なコード生成や高精度な映像生成が求められるなか、業界のニーズに応える製品となる見通しだ。
エヌビディアはこの新型チップと関連AIインフラに対し、初期段階で1億ドルの投資を行う方針を示しており、AI処理で発生する「トークン」使用量に応じて50億ドルの収益が発生する可能性があるという。
※バイブ・コーディング:AIによるリアルタイムなコード生成手法。人間との対話や文脈に応じた柔軟な出力が可能とされる。
「ルービンCPX」が切り拓く生成AIの未来、デメリットも予想
「ルービンCPX」の強みは、従来のGPUでは対応困難だった処理を高速かつ安定的に実行できる点であろう。
特に商業利用やエンタメ分野などトークン消費の多い領域において、高い競争力を発揮すると予想できる。収益性の高い課金モデルとの親和性も高いと考えられ、産業用途に広く貢献し得る。
ただし、高性能ゆえに導入コストや消費電力が大きくなり、中小企業にとっては導入のハードルが高くなるおそれもある。
また、生成AIによる動画やソフトの活用が進む中で、著作権侵害や倫理的リスクも増大しているため、技術の普及には制度面や社会的合意形成の遅れが障害となる可能性もあるだろう。
それでも今後は、生成AIの商業利用拡大に伴い、動画・ソフト分野を中心に導入が進むと予想される。
高性能処理とトークン課金モデルが融合することで、新たな収益構造が形成される期待がある一方、環境負荷や倫理問題への対応が持続的成長の鍵となるだろう。












