OpenAI、アニメ映画制作に協力 AI活用で制作効率化 カンヌ出品も視野に
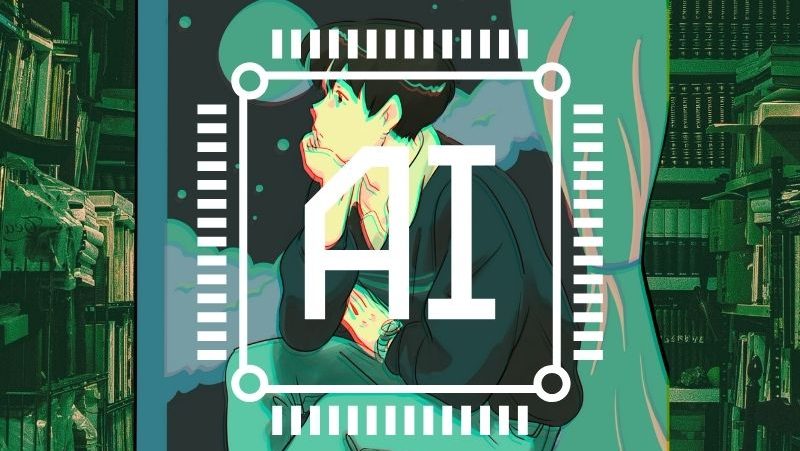
2025年9月7日、米OpenAIがVertigo Filmsと共同でアニメ映画の長編制作に取り組む計画が報じられた。
AI画像生成技術「DALL·E」を活用し、制作コスト削減と新たなワークフローの実現を目指す。2026年カンヌ国際映画祭への出品も視野に入れている。
OpenAIとVertigo Filmsが長編アニメ制作に着手
The Wall Street Journalの報道によると、米OpenAIは英制作会社Vertigo Filmsと協力し、画像生成AI「DALL·E」を活用したアニメ映画を制作する。
対象となる作品は、2023年に短編として公開された「Critterz」を長編化するもので、予算は3000万ドル(約44億円)未満、完成までの期間は約9カ月を予定している。
2026年5月のカンヌ国際映画祭への出品を見据えているという。
短編版「Critterz」は、自然番組を模したパロディー形式で、森の奇妙な生き物がナレーションに反応して会話を始めるというユニークな内容だった。
脚本と監督を務めたChad Nelson氏は、OpenAIのクリエイティブスペシャリストとして活動しており、当時DALL·Eで生成した背景やキャラクターをもとにアニメーションを構築した。
長編版では、人気映画「パディントン 消えた黄金郷の秘密」の脚本家James Lamont氏とJon Foster氏が参加し、物語の世界を拡張するファミリー向けアドベンチャー作品となる予定だ。
制作では、人間のアーティストによるスケッチをAIに入力し、効率的にアニメーション化する工程も検討されている。
AI映画制作の可能性と課題 コスト削減と著作権リスク
今回の試みは、生成AIが本格的に映画制作の現場へ導入される初の大規模プロジェクトとして注目される。
AIを活用すれば、背景やキャラクターデザインの作成を短期間で進められ、従来の工程を大幅に効率化できる。
特に大規模アニメーションでは制作コストが膨大になる傾向があるため、AIの導入は制作期間と予算の圧縮につながると期待される。
一方で、リスクも少なくない。
生成AIの利用をめぐっては、著作権で保護された作品に酷似した出力や、トレーニング素材の扱いに関する訴訟が世界的に増加している。
観客が「AIが作った映画」をどのように受け止めるかという文化的側面も重要であり、単に技術が可能かどうかではなく、受容されるかどうかが成否を左右すると考えられる。
近年の技術動向として、画像生成技術は短期間で飛躍的に進化してきた。
初期のDALL·Eは不自然な画像が多かったが、現在のモデルはより精緻な描写が可能であり、Googleの動画生成AI「Veo 3」なども登場している。
ただし完璧ではなく、今後も精度向上と倫理的枠組みの整備が課題となる。
OpenAIの挑戦は、AI映画制作の実用化と、その是非を問う試金石になるといえる。












