ガバメントAI推進で「デジタル庁2.0」へ 行政組織を強化しAI時代に対応
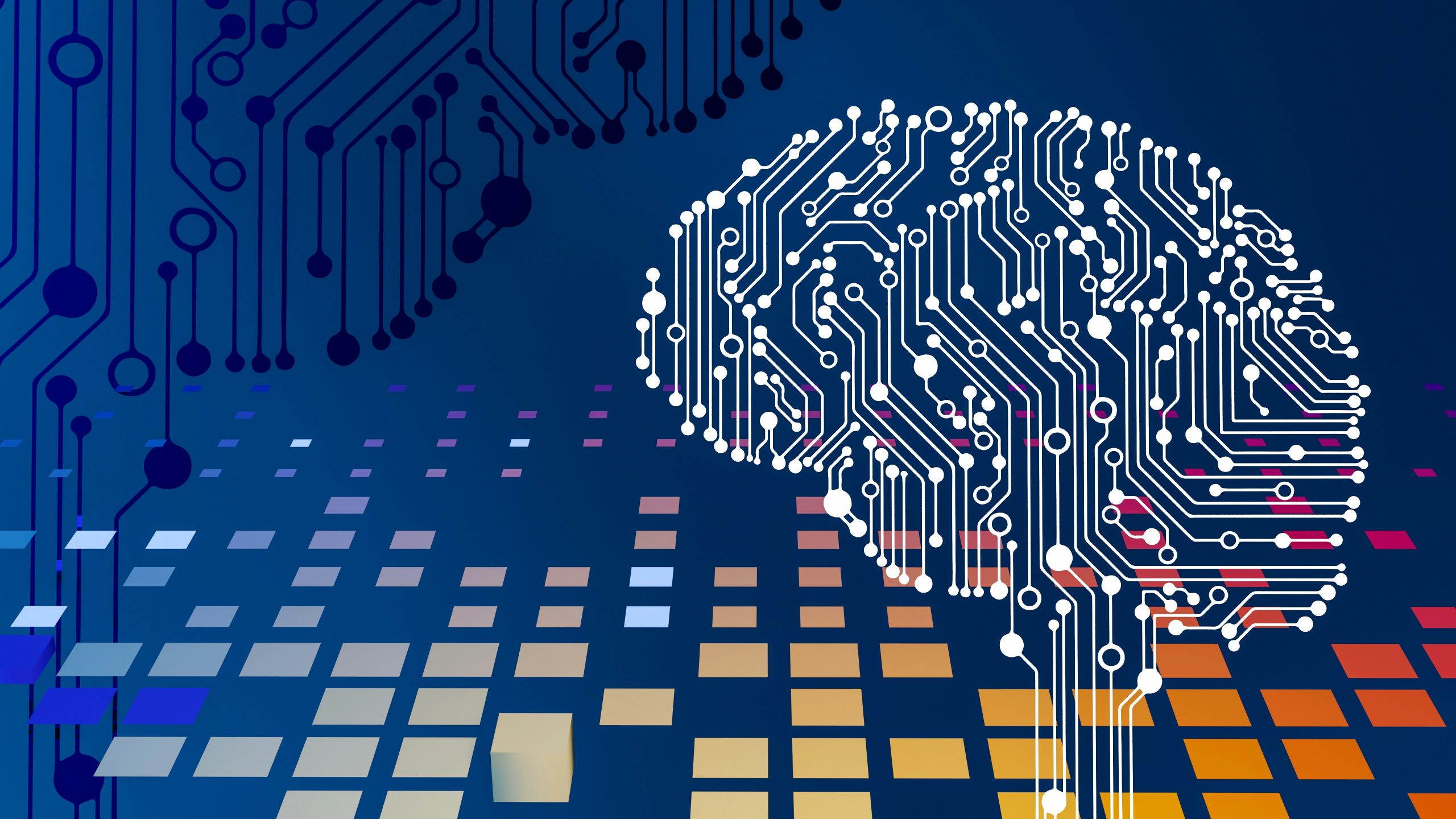
2025年9月5日、デジタル庁は「2025年デジタル庁活動報告」を開催した。
浅沼尚デジタル監は発足から4年間の成果を総括し、ガバメントAIの本格導入や1,500名体制への拡充を含む「デジタル庁2.0」の方針を発表した。
ガバメントAI導入と体制拡大で行政刷新
デジタル庁は2021年の設立以降、行政のデジタル化を進めてきた。
浅沼デジタル監は活動報告において、マイナンバーカードの普及が39%から79%に拡大し、マイナ保険証やマイナ免許証の導入で日常生活における利用範囲が広がったと説明した。
行政手続きも窓口依存からオンライン化へ移行し、業務量削減につながったとした。
制度面ではアナログ規制点検を通じて見直しが進み、業務のデジタル前提化が進展した。
行政インフラとしてはガバメントクラウドやソリューションサービスの導入が進み、自治体システム標準化にも取り組んでいる。
今後の重点分野として、AI活用の徹底、制度ルールの整備、データ利活用基盤の構築、安全なデジタル環境の確立、デジタル人材育成の5点をあげた。
その中核となるのが「ガバメントAI(※)」であり、2026年から本格導入を開始し、将来的に地方自治体への展開を予定している。
デジタル庁はデータ提供、ルール整備、業務支援サービスの構築を担い、活用基盤を整える。
組織面では「デジタル庁2.0」を掲げ、「AI・データを最大限に活用する行政組織」を目指し、職員数を1,500名規模に拡大する。
政策立案を担う官房機能と、システム開発などを担う企画機能を分担し、体制強化を進める。
さらに、利用者体験を重視した内製開発を推進し、政策立案から実装までの時間短縮を図る。
※ガバメントAI:行政機関がAIを活用するための政府基盤。データ提供やルール策定、業務支援を含む。
AI行政の利便性とリスク 今後の焦点
ガバメントAIの導入は、行政手続きの効率化や国民生活の利便性向上につながる利点がある。
窓口業務の削減や迅速な対応が期待され、行政リソースを戦略分野に集中できる点も大きい。
さらに、データ利活用やAIの制度的整備は産業界にも波及し、デジタル経済の競争力強化に寄与する可能性がある。
一方で、リスクも存在する。
AI導入に伴うコスト負担やシステム障害のリスク、データ管理の不備によるセキュリティ問題が懸念される。
また、国民のデジタルリテラシー格差が進めば、サービス享受の公平性に影響を与える可能性もある。
人材確保についても、AI専門人材の不足が制度実装のボトルネックとなり得る。「デジタル庁2.0」が目指す高速な政策立案と実装の仕組みは、日本の行政に大きな変革をもたらすだろう。
しかし、その成否は国民への浸透度合いや、持続可能な運用体制の確立に左右されると考えられる。
利便性とリスクの双方を見極め、バランスの取れた推進が求められる局面にあると言える。












