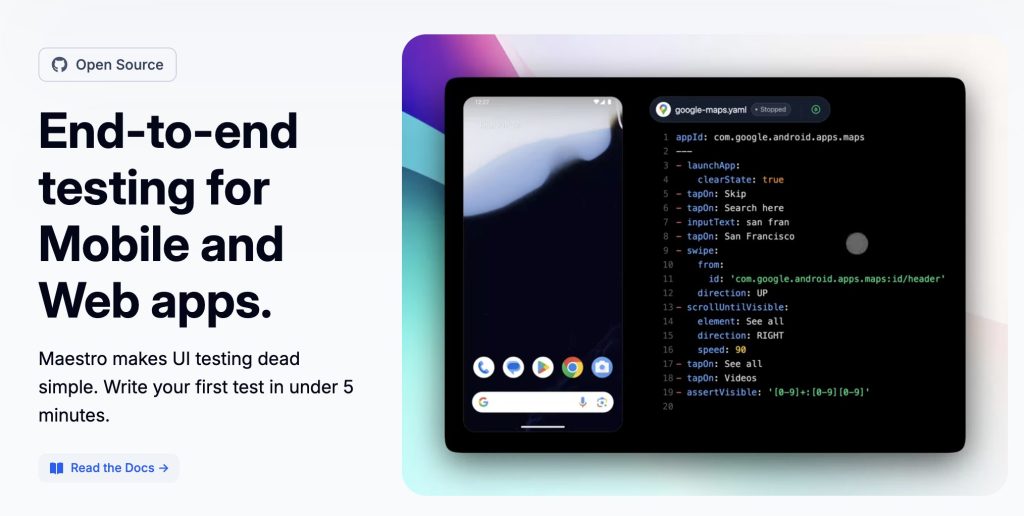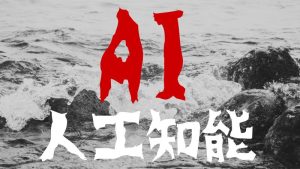NTT、純国産AI「tsuzumi 2」を10月公開 GPT-4o並の日本語力で業務支援強化へ

2025年8月6日、NTTは純国産大規模言語モデル(LLM)「tsuzumi」の次世代版「tsuzumi 2」を10月にリリースすると発表した。GPT-4oと同等以上の日本語理解能力を備え、企業の業務支援や社内文書解析の精度を大幅に向上させるとしている。
GPT-4o並の精度実現 「tsuzumi 2」が国産AIの旗手に
NTTによると、tsuzumi 2は日本語の文脈・文意理解力が大幅に強化された。
パラメータ数は7B(70億)から30B(300億)に拡大され、より複雑な言語処理が可能となった。
島田明社長は決算説明会で、経理マニュアルなどの問い合わせ対応精度が前モデル比で4倍向上したと説明。オンプレミス環境に対応しており、1GPUで動作するコストパフォーマンスの良さも維持、セキュリティ性も高いという。
日本語性能のベンチマーク評価では、同サイズ帯のLLMの中でトップを記録。さらに、GPT-4oのような大規模モデルと比較しても同等以上の日本語理解力を示した。tsuzumiは16言語程度を学習させているが、商用化は現時点で日本語のみとなっている。
価格と性能を両立 企業の国産AI導入を後押し
tsuzumi 2の登場は、国産LLM開発競争の新たな局面を切り開く可能性がある。
特に「特定業務への適用」「自社インフラとの連携」「低コスト運用」の3点は、導入に慎重だった企業の背中を押す要因になり得るだろう。
実際に、すでに導入実績は約800件に達しており、特定領域での活用は着実に広がっている。
今後は、FAQや社内文書検索にとどまらず、医療・法務・自治体など精緻な日本語処理が不可欠な分野への応用が期待される。さらに、政府の国産AI支援政策と連動すれば、普及が国策レベルで加速する可能性もある。
一方、tsuzumiシリーズの課題は、英語や中国語など多言語対応が現時点で行われていないことだろう。
中長期的には、tsuzumiが「日本語特化型の高精度LLM」として地位を固めつつも、特化と汎用性のバランスをどう取るかが焦点になると考えられる。
生成AIがグローバル基準で進化する中、総合性能で海外勢にどこまで迫れるかが、日本発LLMの真価を測る分岐点となるだろう。