AI多用職場で燃え尽き症候群のリスク増 生産性向上の裏に潜む人間関係の希薄化
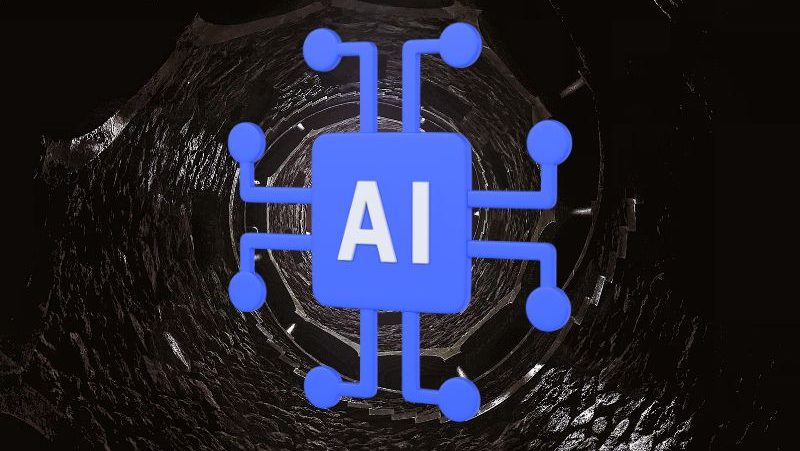
2025年7月9日、米フリーランス仲介大手Upworkが発表した国際調査により、AIツールを積極的に活用する職場では、常勤従業員の燃え尽き症候群のリスクが大幅に上昇していることが明らかになった。
生産性は高まる一方で、心理的安全性の喪失という新たな課題が浮かび上がっている。
AI活用が心理的負荷を助長 退職リスクは2倍に
フリーランス仲介大手Upworkが複数の国の労働者2500人を対象に行った調査によれば、AIツールを日常的に活用する常勤従業員は、そうでない従業員に比べて燃え尽き症候群(※)のリスクが88%高く、離職意向も2倍に達していることが明らかになった。
AI導入により業務効率が高まる一方で、従業員のメンタルヘルスに負荷がかかっている可能性が浮上している。
とくにAIをよく使う常勤社員においては、チームとのつながりが薄れることで心理的安全性が損なわれていると指摘されている。
一方、同じくAIを利用する立場であるフリーランスの88%は「AI活用がキャリアに好影響を与えている」と回答。
自由な裁量や人間関係の少なさが、AIとの関係性をポジティブに保つ要因となっていると分析されている。
またレポートでは、職場における人間関係の変化も指摘。
対象者のうち85%がAIに人間の同僚より丁寧に接しており、67%はAIのほうが信頼できると答えた。
職場におけるAIの重要性が増す一方で、対人関係の希薄化が進んでいることを示している。
Upworkは「AIで高い生産性を達成している労働者が、労働体験の基盤である心理的安全性とチームのつながりの感覚を失っており、これが燃え尽き症候群や離職の意向の原因になっていることを裏付けている」と述べている。
※燃え尽き症候群:慢性的なストレスにより、心身の疲労、意欲の喪失、感情の枯渇などが生じる心理的状態。特に対人関係や高負荷な業務環境で発生しやすい。
つながりの希薄化が離職を促進 AI時代の職場課題
AIの導入は業務効率や情報処理能力の向上に寄与し、多くの企業にとって競争力強化の鍵となっている。時間やコストの削減、品質の安定化といった明確なメリットがある一方で、今回の調査はその“副作用”を明らかにしたと言える。
2025年5月にHarvard Business Reviewが発表した報告でも、生成AIの活用が「仕事の意義を感じにくくする」との指摘があり、生産性向上と人間的な充足感の間に乖離が生じている可能性が示されていた。
この傾向が進めば、従業員は形式的な成果だけを追い求めるようになり、やがて「なぜこの仕事をするのか」という根本的な問いに空白が生まれる恐れがある。
加えて、AIとの信頼関係が深まる一方で、人間同士の共感や対話が軽視されるようになれば、組織内の人間関係は表層化し、心理的な孤立感は増幅するだろう。
今後、企業がAI活用を進めるにあたっては、テクノロジー偏重の姿勢に対して慎重になり、人間同士のつながりや感情を意識した職場設計が求められる。
AIと共存する時代においては、生産性と人間性のバランスをどう保つかが、経営の重要課題になると考えられる。












