神奈川県、NFT活用した科学体験イベントを拡大 スタンプラリーに18施設が参加し7月19日開始
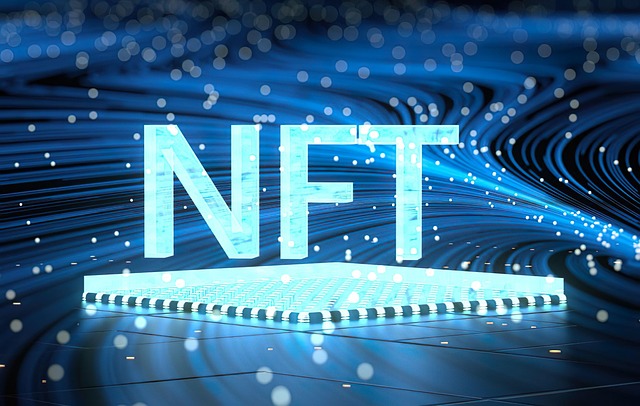
2025年7月19日、神奈川県はNFTを活用した科学体験イベント「サイエンスかながわ 2025デジタルスタンプラリー」を開始する。
対象施設は昨年の6倍にあたる18カ所に拡大され、スマートフォンを通じてLINE上でNFTスタンプが取得可能となる。
NFTスタンプで科学体験を促進 対象施設は6倍の18カ所に拡大
神奈川県は、次世代のイノベーション人材育成を目的とした「サイエンスかながわ」を展開し、その一環として「デジタルスタンプラリー」を7月19日から12月27日まで実施する。
2024年に開始したこの試みは2年目を迎え、対象施設数が前年の3カ所から18カ所へと大幅に増加した。
イベントでは、県内の科学館や企業ミュージアム、大学施設などに設置されたQRコードをスマートフォンで読み取ることで、NFTのデジタルスタンプを取得できる。
NFTはLINEを通じて発行され、ユーザーは特別なアプリをインストールすることなくコレクションを楽しめる仕組みとなっている。その特性上、改ざんが困難で、デジタル上でのコレクション性や達成感を高めやすく、体験学習への動機づけとして有効だ。
対象施設は、横浜・川崎・湘南など6地域にわたって分散されており、科学技術に関連する教育拠点に加え、企業による技術展示や地域博物館も含まれる。
さらに、NFTを3つ以上集めた参加者の中から抽選で、理化学研究所などで開催される特別イベントへの参加機会も用意されている。
この取り組みは、NFTの製作やスタンプラリーの運営をデジタルガレージが担当し、NFTの配布にはキリフダの提供するLINE連携技術が活用されている。
NFT×科学教育の可能性と課題 地域活性とITリテラシー向上に寄与するか
今回の神奈川県の取り組みは、地方自治体によるNFTの社会実装としても注目に値する。
今後、デジタルスタンプラリーが定着し、収集体験の中に教育的要素を組み込むフォーマットが確立されれば、他県への横展開や、観光・文化施設を巻き込んだマルチジャンルの展開も現実味を帯びてくる。
一方で、NFTという技術自体がまだ一般層に浸透しきっていない現状を踏まえると、技術的な理解の格差や、保護者世代への説明不足といった課題も指摘される。とはいえ、専用アプリ不要で参加できる設計は、こうした障壁を低減する工夫として評価できる。
今回の取り組みはまた、県内の多様な科学施設をめぐる動機づけにもなっており、地域経済や観光面への波及効果も見込まれる。参加者がNFT取得を目的に複数拠点を訪れることで、従来はアクセスが限られていた施設にも新たな流れが生まれる可能性がある。
こうした事例が実績を積めば、他の自治体でもNFTを用いた地域振興施策が広がる契機となるだろう。
科学教育と先端技術、地域資源を結びつけるモデルケースとして今後の展開に注目が集まる。
サイエンスかながわ:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bs5/cnt/f7414/index.html












