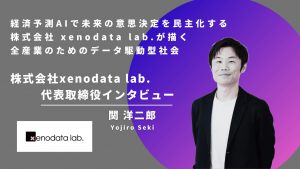経済予測AIで未来の意思決定を民主化する。株式会社 xenodata lab.が描く全産業のためのデータ駆動型社会
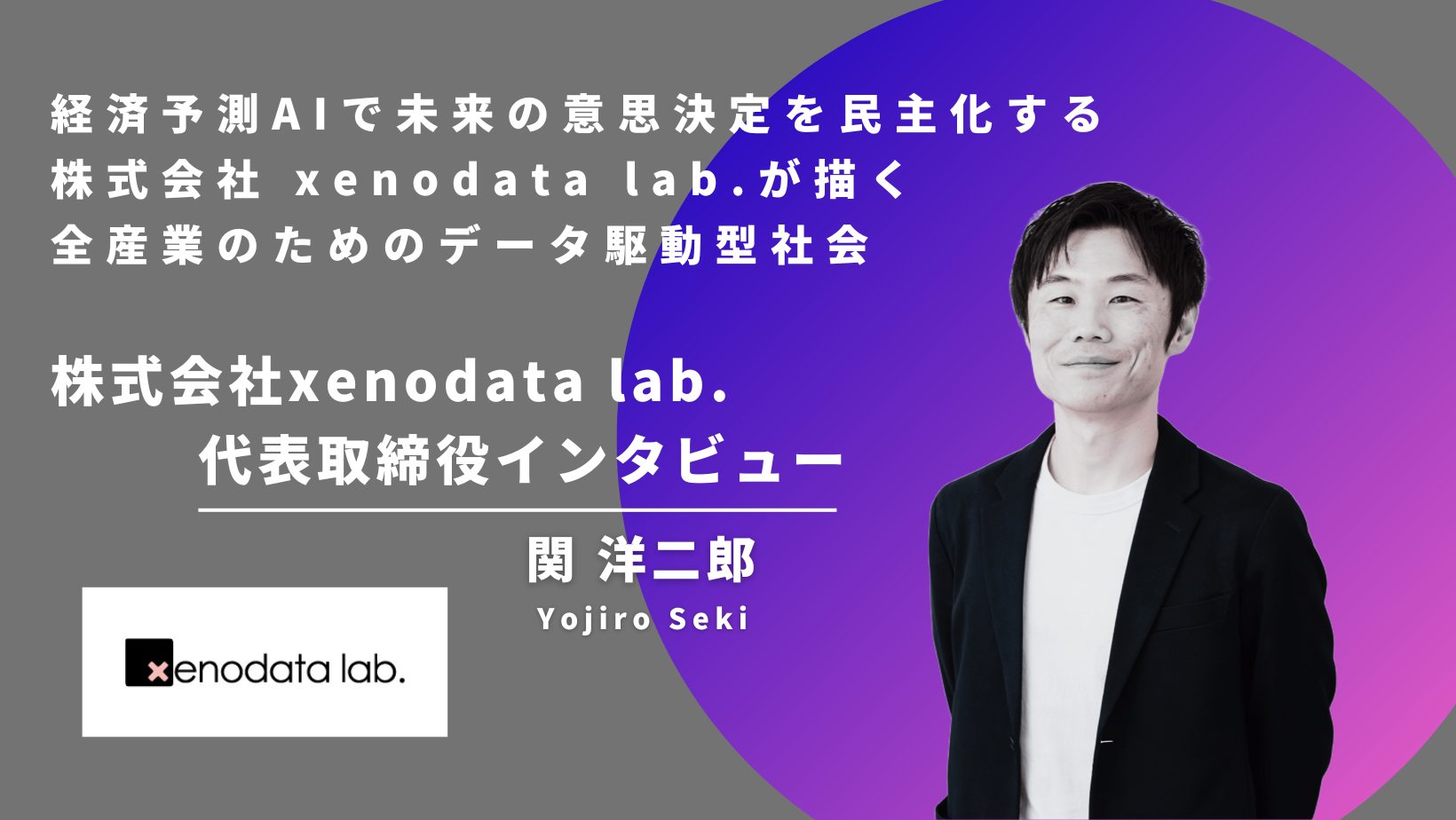
株式会社 xenodata lab.(以下、xenodata lab)は、経済×予測という領域に特化し、経済データの未来を可視化する独自のAIプロダクト「xenoBrain」を展開するスタートアップです。
5万を超える経済指標を毎週自動予測するという前例のない取り組みにより、企業の経営判断や調達・金融分野における意思決定を進化させてきました。現在は大企業や金融機関を中心に導入が進み、IPOを見据えた事業フェーズに突入。創業以来フルリモートを徹底しながらも、極めて高い生産性と組織カルチャーを維持している点でも注目を集めています。
今回は、xenodata labのFounder/CEOである関 洋二郎氏に、創業の背景、経済予測AIという挑戦的な領域で培ってきた独自技術、そしてこれからの展望や共に未来を創る仲間像についてお話を伺いました。
関 洋二郎(せき ようじろう)
株式会社 xenodata lab.代表取締役社長。2008年、株式会社ユーザベースに参画し「SPEEDA」の事業開発責任者として、サービスの立ち上げからグローバル展開、特にアジア市場への進出を牽引。経済情報の収集・整理から一歩進んだ「予測」への可能性に着目し、2016年に株式会社xenodata lab.を設立。
経済予測プラットフォーム「xenoBrain」を開発・提供し、5万超の経済指標をAIで週次予測する独自技術をもとに、大手事業会社や金融機関への導入を拡大中。現在はプレIPOフェーズにて、経済予測の社会実装と新たな経済インフラの創出に取り組んでいる。
経済予測で世界を変える──xenodata lab関氏が語る創業の原点と挑戦
——まず、創業の経緯や会社を起業した背景について教えてください。
関氏:創業のきっかけは、前職の株式会社ユーザベースでの経験にあります。私はスピーダというサービスで、世界中の経済情報を集めて検索できるプラットフォームを作る事業に携わっていました。やっていくうちに、ユーザーのニーズが広がり、日本だけでなく海外やアジアへと展開する方向に向かっていました。ただ、私は横に広がるよりも、もっと縦に掘り下げて、データを使って未来を予測していく方向に強い可能性を感じていたんです。
2014年頃、日本ではまだAIという言葉がSFの中の話のように扱われていた時代に、私は海外のテック企業の中に、経済データとAIを組み合わせて、革新的なことをしていた会社がありました。その記事を読んで「これだ!」と思ったんです。経済データとAI、特に深層学習や機械学習といった技術を組み合わせれば、新しい産業が立ち上がると確信しました。それがものすごくワクワクして、自分でやってみたいという気持ちが強くなり、退職してxenodata labを立ち上げました。
——AIやブロックチェーンなど、技術選定の段階でも色々とお考えがあったと伺いました。
関氏:当時、AIかブロックチェーンのどちらに取り組むかという選択肢がありました。実は仮想通貨取引所の立ち上げもアイデアとしてはありました。ただ、マウントゴックスの破綻が話題になっていた時期でもあり、仮想通貨の将来性は感じていたものの、仮想通貨以外のブロックチェーンを軸とした事業としてはまだ難しいと判断しました。自分のキャリアや経験を活かせる分野として、経済データとテクノロジーの融合にこそ勝機があると感じていました。「世界で一番になれるかもしれない」という想いで、この道を選びました。
——創業時のプロダクト開発について、どのように進められたのでしょうか?
関氏:本当に幸運だったのは、非常に優秀なエンジニアたちが集まってくれたことです。今と違って、当時はエンジニアの数も限られていて、ビジネスアイデアがあっても技術者がいないために起業できないケースが多くありました。あるいはスキル不足のエンジニアと組んでしまい、結局プロダクトが形にならない、ということも少なくなかったです。そのような中で、あれだけの人材が揃ったのは、本当に運が良かったとしか言いようがありません。
唯一無二の経済予測AI──「xenoBrain」の予測技術と独自性
——貴社の事業は「経済×予測」というドメインに特化されているのが非常にユニークだと感じます。
関氏:まさにその通りで、私たちは、「経済×予測」に特化した会社であり、経済データにおける予測という非常に専門的なドメインにフォーカスしています。経済データを収集してExcelで見やすくするようなことではなく、AIを使って経済の将来を予測するということに集中している、ちょっと珍しい会社だと思います。
——競合他社との違いや、xenodata labならではの独自性について教えてください。
関氏:独自性という意味では、まず同じドメインに取り組んでいる企業が他にほとんどいないという点です。経済の予測をここまで広範囲にやっているのは我々だけです。強みは、予測の精度や、その解釈性を高める技術です。私たちは既存の手法を真似するのではなく、独自のアイデアで進めてきました。だから他社が真似できないし、真似する必要もないという感じですね。
現在、我々は5万の経済指標を毎週予測しています。もちろん全部が当たるわけではありませんが、これだけ多岐にわたる指標を同時に、かつ継続的に予測しているということ自体が他にはありません。これは従来の時系列予測モデルでは非常に難しいことなので、私たちは独自のアルゴリズムやデータ処理の工夫で対応しています。
——すでに多くの企業で導入が進んでいますが、具体的な事例についてもお聞かせいただけますか。
関氏:たとえば、大手電力株式会社 資材部の皆様には、資材価格の高騰や物価上昇への対応策として「xenoBrain」を導入いただいています。従来は業界紙やニュースを中心に市場動向を把握していたものの、情報の幅や深さに限界を感じられており、より広範な経済データとAIによる予測を取り入れることで、調達戦略の高度化を図りたいという思いから導入を決定されました。
銅やアルミなどの原材料価格や、変圧器・遮断器といった電力関連資材の価格予測を重視されており、調達のタイミング判断を支援する材料や、市場在庫の予測データなども加味することで、価格上昇や納期遅延を見越した戦略的な早期手配の検討にも役立てられています。さらに、xenoBrainの業界別企業一覧やマーケットシェア分析機能を使い、新規サプライヤー開拓の情報収集も効率化されており、従来手作業で行っていた業務の負担軽減にもつながっています。
フルリモート組織で挑むIPO準備──xenodata labの事業フェーズと人材戦略
——現在の事業フェーズと、それに合わせた組織体制について教えてください。
関氏:現在は、いわゆるプレIPOのフェーズにあります。まだ上場直前というわけではありませんが、その一歩手前という認識です。組織体制としての特徴は、全社フルリモートであることです。これはエンジニアに限らず、ビジネスサイドの社員も含めた全員が対象です。物理的なオフィスは一応あるのですが、実質的には使っておらず、全社員がリモート勤務を前提に働いています。
——フルリモートを実現できている背景や、そこに根付く文化とは?
関氏:創業時から私以外は全員エンジニアという体制で始まり、もともとプロダクト開発志向の文化がベースにありました。コロナ禍をきっかけに物理オフィスは完全に不要だと判断し、「コロナが終わっても戻さない」と決めてからは、フルリモートを前提に人を採用するという方針を徹底しています。
この体制がうまく機能しているのは、社員の多くが「真面目で貢献意欲の高い人たち」だからです。モニタリングなしでも業務が回るのは、サボることなく、限られた時間を使ってよりチームに貢献しようとする姿勢が組織全体に浸透しているからです。働くこと自体がチームのためであり、自己実現でもあるという文化が根付いています。
——採用面では、どのような人材が集まっていますか?
関氏:興味深い点として、エンジニアは全員男性、非エンジニアは全員女性という非常にユニークな構成になっています。特に非エンジニアの方は家庭を持つ方も多く、フルリモートという働き方が大きな魅力になっていると感じます。エンジニアに関しては、ここ5年間で1人も採用していません。というのも、ほぼ誰も辞めていないからです。フルリモートでもモチベーションが高く、やりがいを感じながら長く働ける環境になっていると自負しています。
——ビジネスサイドの採用はどのように進められていますか?
関氏:ビジネスサイドは、事業のフェーズに応じて必要な役割が変化するため、IPO準備に伴い経理経験者や、売上成長を加速させるためにセールス担当者を中心に進めています。基本的にはリファラルで進めてきましたが、最近は限界を感じており、スカウトを中心に採用活動を行っています。
——今後の組織づくりに向けた展望は?
関氏:組織規模を一気に拡大することは考えておらず、引き続き最少人数で最大成果を出すテクノロジードリブンの組織を目指します。とはいえ事業の進展とともに必要な役割のバリエーションは確実に増えていますので、今後もフルリモートというカルチャーに共感し、主体的に貢献できる人材と出会っていきたいと考えています。フルリモートであっても強いチームが作れるという実例を、これからも示していきたいと思っています。
経済予測で世界を変える──xenodata labが描く未来と求める人材像
——今後の事業展開について、どのような構想をお持ちですか?
関氏:現在展開しているのは、事業会社や金融機関向けのBtoBサービス「xenoBrain」です。これまでは、人がデータを見て自ら判断するというのが主流でしたが、今後はAIが経済を予測し、それをもとに人が行動を決めるという時代になるのは間違いないと思っています。LLMがここまで発達してきた今、それがいよいよ現実味を帯びてきました。
我々が目指しているのは、経営者や経営層がAIの予測を見て意思決定する世界の実現です。これは我々がやらなくてもいずれ誰かがやることですが、今の日本でそれを実現できるのは私たちしかいないと考えています。そのビジョンをやり切ることが、我々のミッションです。
今後の展開としては、まず大企業向けのBtoB領域で確実に勝ち切ること。その上で、中小企業向けにサービスを展開し、AI予測をより多くの人に届けられるようにすることを目指しています。そして将来的には、BtoC領域にも進出し、投資や日常の意思決定など、より広い場面で予測を役立てられる世界を実現したいと考えています。これらはIPO後の展開になりますが、経済予測の価値を社会全体に広げていく構想を描いています。
——その未来を実現するために、どのような人材を求めていますか?
関氏:我々の事業である「経済の予測」というのは、非常に普遍的なニーズを扱っています。誰もが未来を知りたいと思っているわけですから、課題設定自体はシンプルです。大事なのは、それをやり切れるかどうかです。だからこそ、長期的な目線を持ち、本質的な価値に向き合い続けられる人を求めています。
もちろん、成長や給与などのモチベーションを持つことも否定しませんし、我々も給与が最も高い会社を目指すつもりで経営しています。ただ、それ以上に「自分たちの取り組みが世の中にどう影響するのか」「課題をどう解決しうるのか」というビジョンや理念に共感し、そこにワクワクできる人に加わってほしいと思っています。目先の成長や自己実現も大切ですが、それと同じくらい「自分たちの仕事が社会をどう良くしていくか」という問いに真剣に向き合える人。そんな仲間と一緒に、これからのフェーズを築いていきたいと考えています。