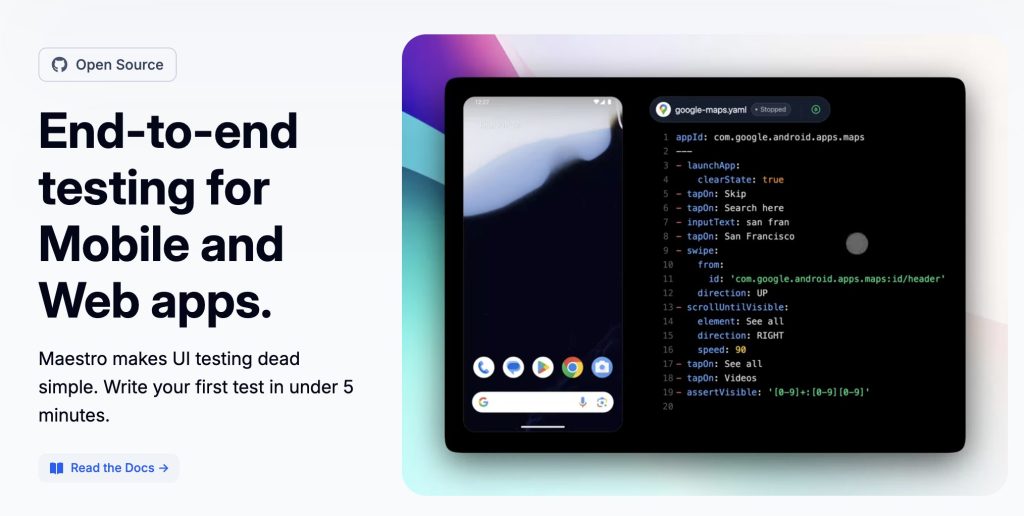AIチャット相談、柏市の教育現場で93.6%の満足度を達成

千葉県柏市の教育現場で試験的に導入されたAIチャット相談システムが、児童生徒から93.6%という高い満足度評価を得たことが、2025年3月25日の発表で明らかになった。
2024年10月から2025年2月までの約3ヶ月間、市内のパイロット校で実施された取り組みでは、従来の相談窓口と比較して10倍以上の相談が寄せられたという。
深刻化する教育課題への新たな対応策として注目される生成AI活用
日本の教育現場では、いじめや不登校、児童虐待などの問題が年々深刻化している。
こうした状況に対し、柏市教育委員会と株式会社ZIAIが共同で実施したAIチャット相談システムの試験導入は、教育支援の新たな可能性を示すものと言えよう。
システムの最大の特徴は、生徒が24時間いつでもどこでも悩みを相談できる点にある。
実施期間中に記録された総相談時間は275.4時間、対話の総ターン数は3,758回に上った。
1回の相談につき平均9ターンの対話が行われており、生徒たちが継続的に悩みを打ち明けていたことがわかる。
このシステムは傾聴を行うだけでなく、生徒の悩みの共感的理解や、必要に応じて教員やスクールカウンセラーへの橋渡しも行う。
早期に課題を発見し、適切な初期対応への道筋をつけることを目指したものだ。
生徒からの反応は肯定的なものが多かったといい、「先生や家族に言えないことも、AIになら簡単に言える」「相談しても、誰にもばらさないから安心」といった声が寄せられている。
なお、システムを提供したZIAIの担当者は、このAIチャットは教員やカウンセラーの代替ではなく、あくまで初期接点として位置づけられるべきだと強調している。
AIチャット相談システムのメリット・デメリット
千葉県柏市におけるAIチャット相談システムの導入は、教育現場における生成AIの活用が実効性を持ち得ることを実証した好例だ。
24時間いつでも相談可能という時間的な自由度、そして匿名性による心理的安全性は、従来の人対人の相談環境では得難い利点である。特に思春期の子どもにとって、羞恥心や不信感が相談のハードルとなりやすいことを踏まえれば、AIという相手の「感情を持たない中立性」がプラスに作用したと見るべきだ。
一方で、AIの応答内容の質と限界は懸念点と言える。共感や適切な助言を装うことはできても、最終的な判断や感情の微細な揺れに完全に対応するのは難しい。AIが安易な慰めや誤った一般論に留まってしまえば、生徒が誤った方向に導かれる危険性もゼロではない。
また、AIを介したことで深刻な問題の本質が教員や専門家に正確に伝わらず、支援のタイミングを逸するリスクも指摘できる。
さらに、満足度の高さ自体が“AIで十分”という誤認に繋がる可能性もある。提供企業側が述べている通り、AIはあくまで初期接点であり、人的支援との連携が前提でなければ本末転倒になりかねない。
生徒の悩みを受け止め、必要に応じて適切な人的支援へつなげる補完的役割を果たすことこそが、システムの真価と言えるだろう。
参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000124477.html