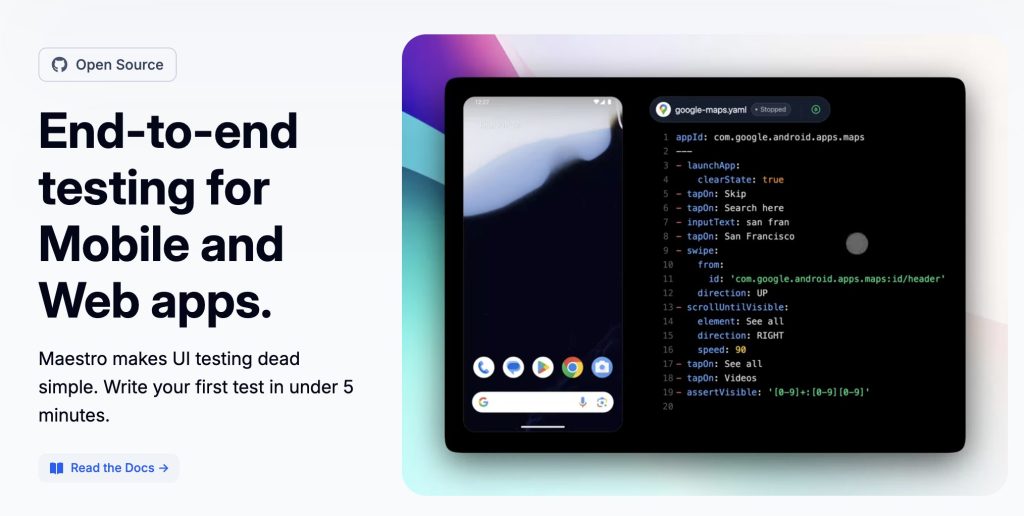大学生の5割が生成AIを継続利用、学業への影響拡大

全国大学生活協同組合連合会が2024年10月から11月に実施した調査によって、大学生の50%が生成AIを継続的に利用していることが、2025年3月3日にわかった。
前年の30%未満から大幅に増加しており、特に授業や研究、論文・リポート作成の参考として活用する学生が多い。
この結果は、生成AIが大学教育や学術研究に与える影響を示す重要なデータである。
生成AIの利用率が急増、学業支援のツールに
全国大学生活協同組合連合会は、大学生の生活実態を把握するために定期的に調査を実施している。近年、生成AIの利用が急増していることを受け、その実態を明らかにする目的で、全国31の国公私立大学に通う学部生11,590人を対象に調査を行った。
その結果、大学生の50%が「チャットGPT」などの生成AIを継続的に利用していることが判明した。前年は30%未満であったため、1年間で大幅に増加したようだ。
一方、利用経験があるが現在は使用していない学生は18%、今後使ってみたいと考えている学生は19%だった。「今後も利用しない」と回答した学生は12%にとどまった。
特に、生成AIの利用目的としては「授業や研究」(32%)や「論文・リポート作成の参考」(30%)が上位を占めている。これにより、生成AIが学業の補助ツールとして認識されていることが分かる。「翻訳・外国語作文」(19%)、「遊び・興味」(19%)、「メールなどの文章作成」(12%)といった目的でも利用されているが、主に学術的な用途での活用が目立つ。
利便性と倫理問題、大学生の意見が分かれる
調査では、生成AIを利用する学生からさまざまな意見が寄せられた。
肯定的な意見としては、「情報を効率的にまとめてくれるため、調べ物の時間が短縮できる」「アイデアを整理するのに役立つ」といった声が多い。特に、大量の情報を短時間で整理できる点を評価する意見が目立った。
一方で、否定的な意見も存在する。
「出所が不明な情報が多いため、参考程度にとどめるべき」「課題をAIに一からやらせることは研究倫理に反する」といった懸念が挙げられている。これらの意見は、AIの情報精度や倫理的な側面についての議論の必要性を示している。
今後、生成AIの普及がさらに進む中では、大学教育や研究における適切な活用方法が求められる。大学側は、AIを活用する際のガイドラインを整備し、倫理的な問題に対応することが必要となるだろう。