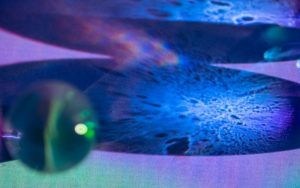ミツカリ、AIと統計で人事戦略を支援する新機能「ミツカリラボ」提供開始

株式会社ミツカリは2025年4月10日、HR Techサービス「ミツカリ」に新機能「ミツカリラボ」の提供を3月25日から開始したと発表した。採用、配置、離職といった人事の重要課題に対し、統計データと生成AIを活用して分析・意思決定を支援する国内向けサービスである。
人事の現場における属人的判断からの脱却を補助
「ミツカリ」は、個人の性格特性や相性をもとに、組織全体のパフォーマンス向上を目指すHR Techサービスである。
今回追加された「ミツカリラボ」では、人事課題の解決を支援するために、「統計機能」と「AIアシスタント機能」の2つを提供している。
「統計機能」は、導入企業および受検者データを横断的に分析できる統計モジュールである。
業種や職種、役職別に絞った分析が可能となっており、自社の傾向を業界全体の水準と比較することで、組織の特徴や課題が浮き彫りになるという。
たとえば、エンゲージメントに関する数値を平均値や標準偏差で表示し、改善が必要なチームや職種を特定できるようになっている。
また、「AIアシスタント機能」は、対話形式で課題の相談が可能なインターフェースが設けられ、性格適性検査の結果をもとに、具体的な配置アドバイスやコミュニケーション上の注意点を提示する。
最大3名の候補者情報を同時に読み込み、相性や配属先とのミスマッチの可能性を事前に可視化する機能も搭載されている。
これにより企業は、より構造的かつ合理的な人事判断、人材の定着率やパフォーマンス向上につなげられるだろう。
HR Techは“使いこなし”が鍵を握る 今後の展望と課題
ミツカリラボのようなHR Techの進化は、今後の人事戦略において一定の影響力を持ち続けると考えられる。特に労働市場の流動性が高まる中では、「採用の精度」や「定着率の向上」は、企業競争力に直結するテーマとなりつつある。
属人的判断から脱却し、科学的根拠に基づく意思決定を促す流れは今後も継続して広がるだろう。
一方で、すべての企業に同じ効果が現れるわけではない。
データの解釈力やAIの提案をどの程度参考にするかといった運用面の工夫も求められる。特に、個別の人間関係や社内文化といった数値化しにくい要素への理解は、AI単独では補いきれない領域であると考えられる。
市場全体としても、HR Techの導入は広がっているものの、ツールの導入=課題解決とならないケースも散見される。
ミツカリの今後の展開としては、ユーザー企業への活用支援の強化や、ダッシュボード機能のさらなる高度化、AIの助言精度向上などが鍵となるだろう。
生成AIの社会実装が進む中、人事という組織の根幹を担う領域においても、テクノロジーの“活かし方”が企業の競争力を左右するフェーズに入ったといえるのではないだろうか。