【Week : 4/14-4/18】リアル×デジタルを組み合わせた事業が加速 スタートアップ資金調達リサーチ
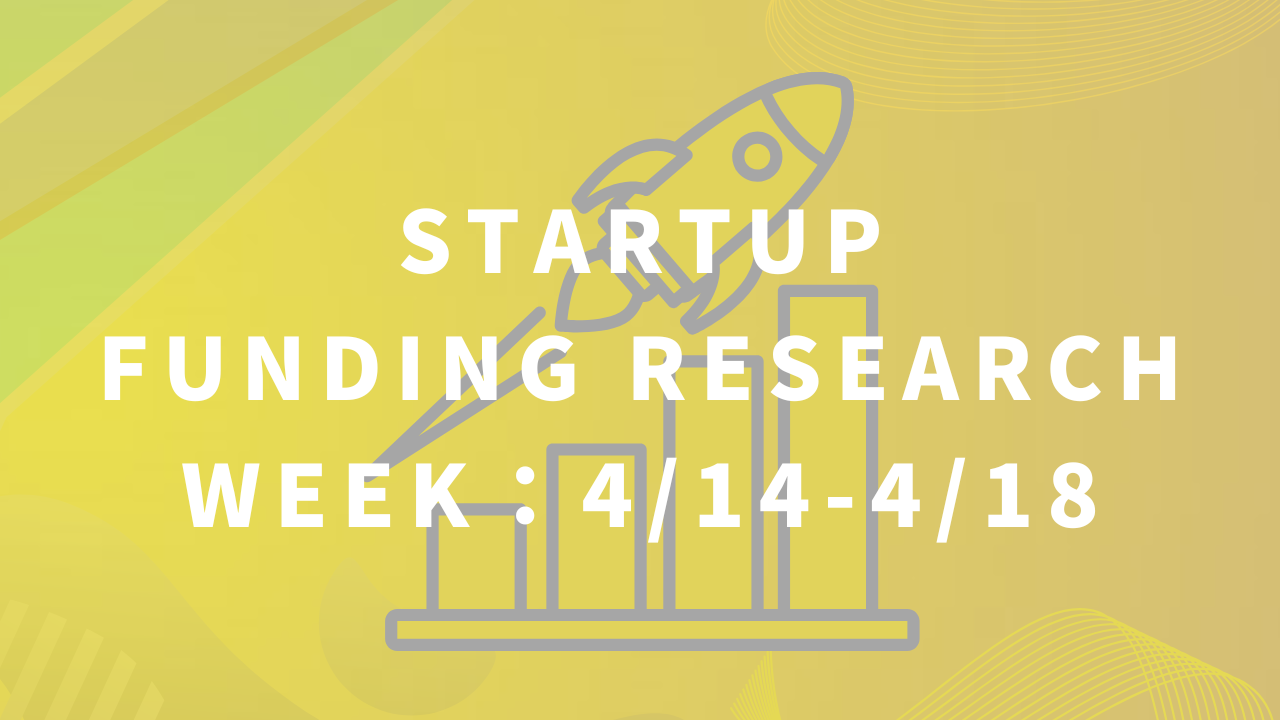
4月が始まり、引き続き様々な分野で活躍するスタートアップ企業が資金調達を発表しました。
この記事では、4月14日から4月18日の間にリリースされた、スタートアップの資金調達ニュースをまとめています。 さらに、事業内容、調達金額、今後の展望についても詳しく解説します。
ARグラスディスプレイやシステムを開発するCellid、11億円の資金調達を実施
事業内容: ARグラス用ディスプレイおよび空間認識エンジンの開発
調達金額: 11億円
引受先: SBIインベストメント、IMMインベストメントジャパン、IMM Investment, Corp.
今後の展望: 国内外の優秀な人材獲得、ARグラスのキーコンポーネント開発強化、量産体制拡充
Cellidは、ARグラス用ディスプレイおよび空間認識エンジンの開発を主軸とした事業を展開しているスタートアップです。特に、世界最大級の広視野かつ軽量のウェイブガイドの開発・設計においては業界最先端の技術を誇り、プラスチック製でフルカラー映像を映し出せる技術開発に世界で初めて成功したといいます。
CellidはARグラスを、より身近な次世代のコンピューター・デバイスとして捉えており、業務の効率化や人手不足などの社会的課題を解決するツールとして、様々な産業での活用を目指しています。昨年は、デザイン性に優れ、軽量なメガネタイプのARグラス、リファレンスデザイン(検証用モデル)を発表し、また今月4月には、視度補正機能を備えたARグラス用レンズのCellid Precision Fit Lenses(プリシジョン フィット レンズ)を発表するなど、ARグラスの進化と普及における取り組みを加速させています。

リアルとデジタルを融合させたWeb3ゴルフゲーム『GOLFIN』を開発するワンダーウォール、10億円の資金調達を実施
事業内容: Web3ゴルフゲーム『GOLFIN』の開発
調達金額: 10億円
引受先: 非公開
今後の展望: 開発体制強化、リアルゴルフ場との連携強化、グローバル展開の加速
ワンダーウォールは、新しいゴルフ体験を提案するWeb3ゲーム『GOLFIN』を手がけるスタートアップです。『GOLFIN』は、リアルとデジタルの融合を通じてゴルフエコノミーを創出することを目的とした、NFTとGPS技術を活用したゴルフゲーム。プレイヤーは、現実世界のゴルフ場と連動したゲーム内で、自分のクラブやアイテムをNFTとして所有・育成でき、ゲーム内でのプレイが資産的価値や実体験と結びつくという、新鮮なユーザー体験を提供します。
すでに全国のゴルフ場との提携を進め、NFT回数券、GPS連動プレイなど、ブロックチェーン技術を用いた新しいゴルフ経済圏の形成を実現しています。ゴルフ場でのプレーが、ゲーム内での成長やデジタル報酬にも連動する仕組みとして影響を与えるような体験設計になっており、ユーザーのゴルフライフに、「オンラインのつながり」や「暗号資産の収益性」をもたらします。さらに、AIを活用したプレーデータの分析やUXの最適化にも一部領域で着手しており、将来的にはユーザーごとのプレースタイルに応じた提案やアドバイスが受けられるなど、プレー体験のさらなる向上を目指しています。

テレプレゼンスシステム「窓」の開発・販売等を行うMUSVI、資金調達を実施
事業内容: テレプレゼンスシステム「窓」の開発・販売
調達金額: 非公開(累計調達金額は7.2億円)
引受先: 住商ベンチャー・パートナーズ、日本政策金融公庫
今後の展望: グローバルネットワークを活かした事業拡大、販売パートナーとの連携強化
MUSVIは、テレプレゼンスシステム「窓」の開発・販売等を行うスタートアップです。「窓」は、大型ディスプレイでの体験を提供する遠隔コミュニケーションシステムで、遠くにいるのに触れそうに感じるほどの臨場感を実現しています。ソニーグループでの研究開発で培った独自の映像・音響・通信技術を組み合わせ、単に全身が映るだけでなく、人が本当にリアルだと感じるための科学的アプローチで「気配」「空気」「雰囲気」といった微妙なニュアンスまで伝えることを可能にしたとのこと。2022年9月の本格的な事業展開から約2年半で国内外600台を超える導入実績があり、鹿島建設や地区宅便など150を超える企業・自治体で活用されています。
「窓」は、オンライン対話の便利さと引き換えに失われがちなコミュニケーションの質を向上させる技術として注目されています。途切れる音声や同時発言の困難さ、小さな画面による視野の狭さ、伝わらない雰囲気や気配といった従来のオンラインコミュニケーションの課題を解決。等身大での映像再現、周囲の音をそのまま届ける音響技術、複数人が同時に発話できる通信技術、目線を合わせるカメラ配置など、細部にわたる工夫により、あたかも同じ空間にいるような自然なコミュニケーションを実現しています。

データとAIでカスタマーサポートを変革するRightTouch、8億円の資金調達を実施
事業内容: カスタマーサポート領域に特化したエンタープライズ企業向けSaaS事業
調達金額: 8億円
引受先: グローバル・ブレイン、GMO VenturePartners、商工組合中央金庫
今後の展望: エンタープライズSaaSにおけるビジネスサイド・プロダクトエンジニアなど全職種の採用強化、生成AI領域への本格展開をさらに進める研究開発
RightTouchは、企業と消費者の間に生じる「問い合わせの煩わしさ」という共通の課題に着目し、カスタマーサポート体験をAIなどを利用して改善するSaaS事業を展開しているスタートアップです。同社の主力製品「RightSupport by KARTE」は、消費者がサポートページを閲覧している段階から行動パターンを分析し、問い合わせる前に適切な解決策を提案することで、消費者の待ち時間とストレスを削減すると同時に、企業側のサポート業務効率化も実現しています。SBI証券やパナソニック、NTTドコモなど大手企業での導入実績があり、一日あたり約3万件の消費者の問題解決をサポートしているとのことです。
カスタマーサポート市場では、消費者の期待値の高まりと企業の人材不足という二つの課題が顕在化しています。従来の「問い合わせを待って対応する」という受動的なモデルでは、消費者はしばしば長時間の待機や何度もの説明を強いられ、企業側も膨大な問い合わせ対応に追われる非効率な状況が続いていました。RightTouchは生成AIを活用し、顧客の行動データ、過去の問い合わせ履歴、企業のナレッジベースなど複数のデータソースを連携させることで、消費者が抱える問題を先回りして解決する「プロアクティブサポート」の実現を目指しています。こうした取り組みは、消費者にとってはスムーズな問題解決体験を、企業にとっては業務効率化とコスト削減をもたらす互恵関係に貢献しています。

Web3プラットフォームを開発するHana Network、3億円の資金調達を実施
事業内容: 暗号資産と法定通貨の取引プラットフォーム開発
調達金額: 3億円
引受先: Mr.Block(Curve Finance)、Mod(Hyperliquid ecosystem)など
今後の展望: 直近のPhase2以降のアプリローンチを数ヶ月以内に実施
Hana Networkは、中央集権取引所に取って代わり、暗号資産と法定通貨の取引を実現するプラットフォームを開発するスタートアップです。2024年10月にローンチした「Hanafuda」というカジュアルゲームアプリは、半年間で累計50万ユーザー・4,000万depositを達成し、インド・インドネシアなどを中心にアジア・アフリカの新興国市場で強い成長を見せています。
今後は3段階のフェーズで、段階的にアプリをローンチする予定になっています。従来は中央集権的取引所(CEX)が暗号資産への入口として業界内で支配的なポジションを占めていましたが、今後は莫大なユーザーを抱えるモバイルインターフェースが取引所に取って代わる暗号資産の新しいディストリビューションチャネルになると予測しています。それに向けて、新興国向けに新たなモバイルアプリケーションのローンチを控えています。

まとめ
4月14日から4月18日のスタートアップ資金調達例をまとめました。
今週の資金調達ニュースからは、テクノロジーを活用して実世界とデジタルの融合を目指す企業が多く資金調達に成功していることが見て取れます。Hana Networkやワンダーウォールのような暗号資産・Web3関連の企業は、単なるデジタル体験だけでなく、リアルな体験と連携させることで新たな価値を創出しています。特に、ワンダーウォールの『GOLFIN』のように、実際のスポーツ体験とデジタルゲームを組み合わせるアプローチは、Web3技術の実用的なユースケースとして注目されます。
また、CellidやMUSVIのように、次世代のコミュニケーションやデジタルデバイスを開発する企業も投資家から高い評価を得ています。特にARグラス技術を開発するCellidに対する11億円という大型調達は、メタバースやAR/VR市場の今後の成長に期待が寄せられていることを示しています。さらに、RightTouchのようなAI技術を活用したエンタープライズソリューション企業への投資も活発で、特にカスタマーサポート分野はAIによる自動化・効率化の恩恵を受けやすい領域として認識されていることが伺えます。全体として、デジタル技術を実世界の課題解決に結びつける企業が投資家から支持を得ている傾向が見られます。
「Plus Web3」では、今後も資金調達例を紹介してまいります。












